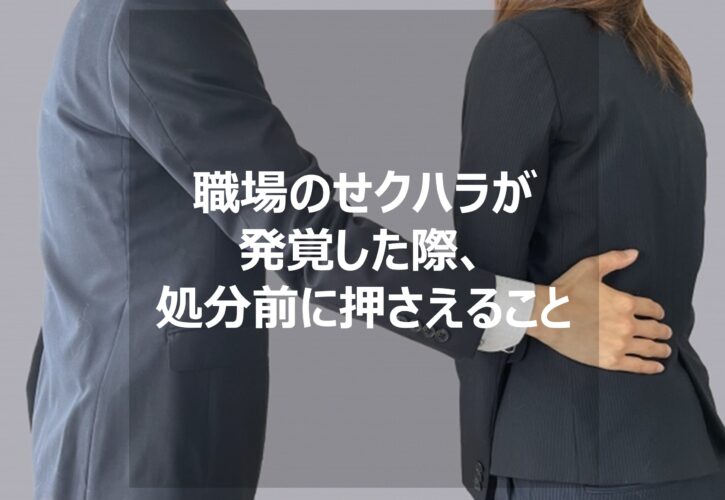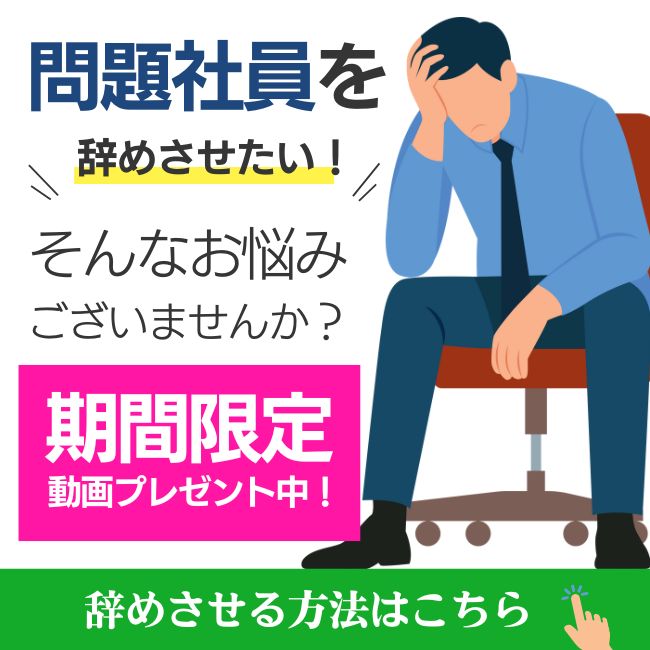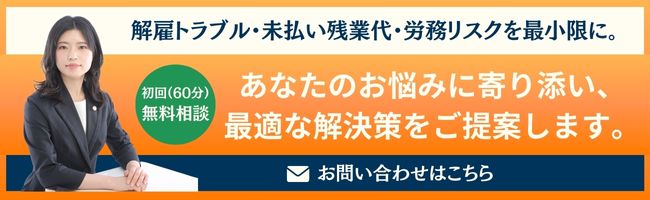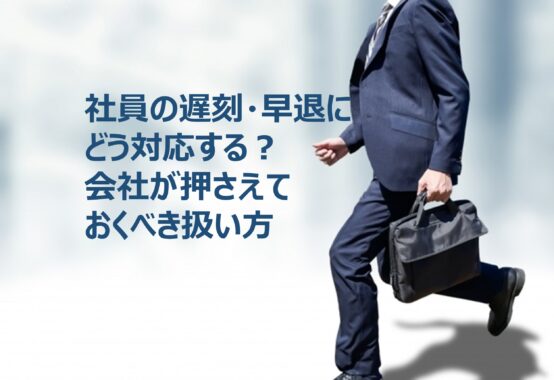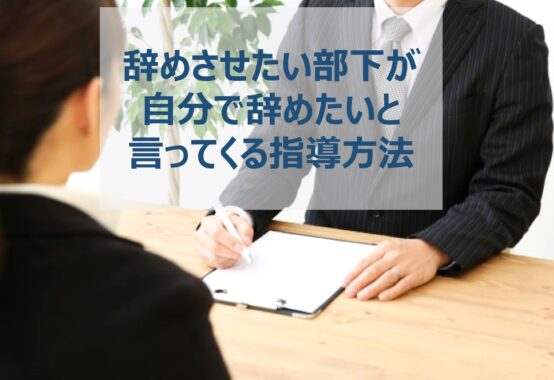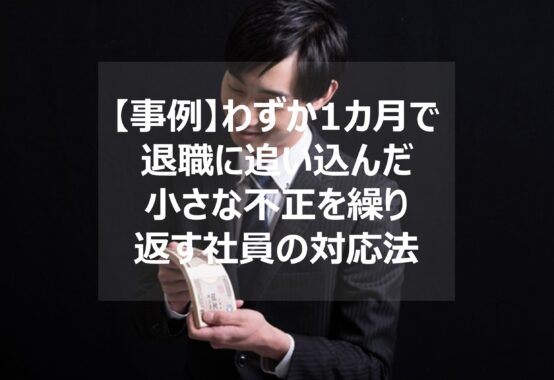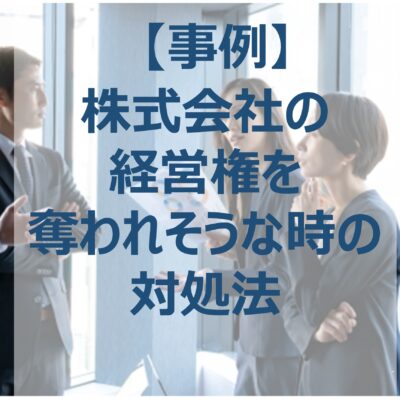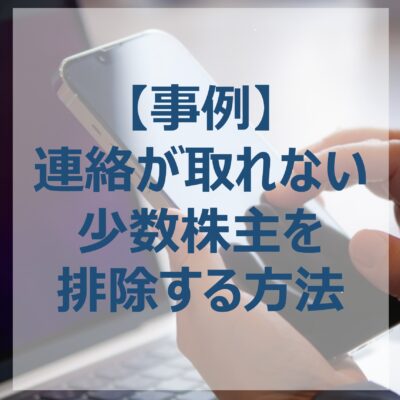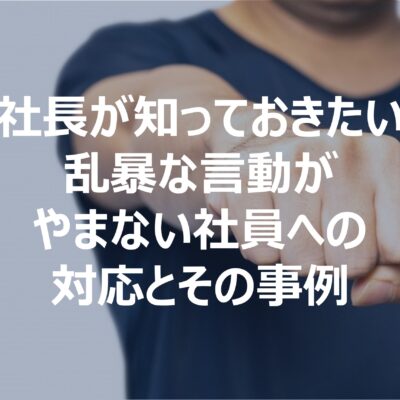「セクハラ」とひとまとめにしても、その程度はさまざまです。職場でセクハラの被害相談が生じた際、会社は加害者の処分だけではなく、被害者、加害者双方に対して配慮しなければいけないことがあります。今回は会社の姿勢、会社が配慮すべき事項についてご紹介します。
1 相談者への配慮
セクハラ被害を訴える相談者が現れた場合、相談者に対し、対応する上でいくつか気をつけることがあります。
(1)プライバシーへの配慮
セクハラの相談があった場合、まず気をつけなくてはならないのは、相談者へのプライバシーの配慮です。プライバシーに配慮された環境で相談を行うこと、セクハラ調査に必要な範囲を越えて情報が漏洩されることはないことを知らせること、対応にあたる人員に誰が予定されているか知らせておくこと、行為者への被害申告内容の開示について同意を得ること、第三者への聞き取りを行う場合に同意を得ておくといった配慮が必要です。
(2)二次被害の防止
相談者の心情に配慮し、なるべく話しやすい環境を作るため、同性による相談対応が望ましいといえます。また、相談に対応した人が先入観に基づく発言をしたり(「勘違いじゃないか」「それくらいのことで」etc)、不躾な発言をしたり、相談者に落度があると決めつけるような発言をしたり、性的表現に配慮を欠いた発言をすると、性的二次被害をもたらす恐れがあります。セクハラの相談者は精神的にも大きな負担を負っていることが多いため、可能であれば産業医や保健師と連携するようにしましょう。
(3)手続きの説明
相談者に対しては、今後どのように手続が進んでいくのかを説明し、それには時間がかかるために最終的な結論が出るまで相談者を待たせることになること、しかし、進捗や成果があったり必要があれば必ず会社から相談者に連絡することを最初に説明しておくと、相談者も事態をうやむやにされないのだと安心することができます。
(4)意思の尊重
行為者に処罰(懲戒)を望むのか、調査中の期間の休職や在宅ワークを希望するのか、職場の異動を希望するのかなど、相談者が何を希望しているのか聴き取り、希望を尊重するようにしましょう。
会社は社員が安心して働けるようにセクハラの予防、調査、再発防止の義務があるため、相談者に「何もしないでほしい」といわれたところで、セクハラ事案を放置できるわけではありませんが、相談者の希望を無視して手続を進めてしまうと、会社に対する不信を招き、紛争を生む原因にもなりますので注意しましょう。
2 聞き取り調査
セクハラ被害の申告を受けた場合、聞き取り調査を実施していくことになりますが、これにもいくつかポイントがあります。
(1)調査の実施義務
会社には、セクハラの有無について速やかに調査を実施する義務があります(セクハラ指針(平成18年厚生労働省告示615号))。もし会社がセクハラ調査をせずに放置した場合、それによって会社が被害者から損害賠償を請求されるリスクもあるため、絶対に事態を放置するようなことがあってはなりません。そのためにも、日頃から相談の担当者や手順を確認してすみやかに初動対応できるように相談体制を整えておきましょう。
(2)対応する人員
セクハラ調査には、当事者から聞き取りを行ったり、証拠の提出を求めたりして、最終的にどのような行為があったのか認定し、それがセクハラに当たるのか、懲戒処分においてどの程度重く見るのかということ評価しないといけません。この認定・評価を適切に行うために、複数人で対応しましょう。また、セクハラの被害者が必ずしも女性に限るわけではありませんが、多角的な検証を可能にするために、対応人員に女性を組み込むことが大切です。
(3)聞取りの順番
聞取りは基本的には、相談者からの聞取り・メール等のやりとりの証拠提出をして、ある程度の全体像をつかんでから、行為者への聞取りに臨み、そして、相談者と行為者の言い分が食い違い、現在確保している証拠に照らし合わせてもどちらの言い分が正しいのか判断できない場合に、聞取りの対象を第三者に拡大させます。
相談者の話を聞く時には、何があったかを調査するということを主眼にして中立の立場で臨みます。そして、相談者の虚偽や思い込み、行為に対する同意があった可能性も念頭に置きつつ、それらを払拭するような事実はあるのかを相談者から調査する姿勢で臨みましょう。もちろん、これらは対応者が頭の中で想定していることですので、相談者に対して「あなたが嘘を言っていないか疑っている」という態度を示さないようにしましょう。
行為者への聞取りを後に行うのは、行為者が最初に自分が調査対象になっていることを知ってしまうと、証拠を隠滅したり、そこまでではないにしても、自己防衛の意識から、相談者に対して相談を取り下げるように懇願したり、周囲に自分はやっていないと話したり、そのように証言してくれと周囲に要望したりすることが考えられるからです。適切な調査を行うためにも、行為者へのアプローチは、相談者からの聞取りが終了してからにしましょう。そして、行為者が相談者とはちがった事実関係を主張している場合には、行為者にも自分の言い分を証明するようなやりとりの証拠があるのかどうか、提出させましょう。ただし、ここで行為者が行為者の言い分に沿うような第三者の証言を提出しようとするなら、それは止めましょう。そのような第三者がいるのであれば、会社からその第三者に聴取すべきであり、行為者がその第三者を抱き込みかねないような事態は防止すべきだからです。
また、行為者への聞取りを後に行うのは、懲戒を見据えた意味合いもあります。もしセクハラ行為があったと認定できた場合には、行為者は懲戒処分の対象になりますので、結果的にセクハラ調査での聞取りが懲戒手続の意味合いを帯びてしまうことがあります。そうすると、懲戒手続なのであれば、セクハラ行為を特定せずに行為者の言い分を聞いただけでは、行為者に十分な反論の機会を与えたことになりません。そのため、相談者からの聞取りや証拠の提出を受けて、ある程度、いつ、何があったのかを特定できた後でなければ、行為者への聞取りを行えないのです。
なお、懲戒手続について後に行為者から会社が訴えられるおそれもない訳ではありませんので、行為者の聴取については必ず、日時、場所、時間、出席者、聴取の概要を記録に残すようにしましょう。
3 証拠の確保
先程もふれましたが、まずは相談者からやりとりなどの証拠を提出してもらいます。行為者も同じく証拠の提出に応じる場合や、相談者と主張が異なる場合には証拠を提出させましょう。
セクハラの内容が、日頃のやりとりなどではなく、宴席などでその場限りでの性的接触であった場合、その日その時に相談者と行為者が同席していたのか、相談者がセクハラ後に誰かにそれを相談したり、婦人科や心療内科への受診をしていたり、警察へ相談しているかどうかを確認し、可能な限り資料の提出を求めましょう。また、その場を目撃している第三者がいるかどうかを確認し、その第三者に対する聞取りを行ってよいかどうか、相談者に了承を得ておきましょう。
4 出勤の調整
セクハラの有無や懲戒処分が決定するまでの間、相談者、行為者どちらか、あるいは双方の出勤を調製する必要があります。相談者の多くは、セクハラ被害を訴えながら、その加害者と今までどおり一緒に働きたいとは思っていませんので、相談者の心情に配慮し、出勤について調整しなければいけません。
(1)相談者の出勤調整
相談者の出勤をどのように調整するか、まずは相談者の希望をきちんと聞取りしましょう。行為者と一緒の空間に居たくはないが仕事を続けたいというのであれば、在宅ワークや部署異動が可能であるかを調整します。精神的に疲弊して仕事に耐えないという状況であれば、医師の診断を取得するよう求めたうえで、休職や傷病手当の利用を検討しましょう。
(2)行為者の出勤調整
行為者を出勤させたままでは、被害が拡大したり、証拠隠滅をするおそれがある場合には、行為者に出勤させない措置が必要になります。在宅ワークにさせる場合もありますが、在宅ワークができない場合には、単なる出勤禁止となります。その段階ではまだセクハラの有無すら確定していない状況のため、会社が一方的に出勤を禁じることになります。その場合は、行為者へ賃金の支払いをしなければなりませんので、注意しましょう。
5 まとめ
セクハラ相談への対応は、単なる個人的なトラブルや個人の感じ方の問題を超えて、複雑な問題であることがわかります。そのため、セクハラ被害にあってしまった際に、会社がどう対応してくれるかがとても重要となります。
また、セクハラを行った者だけでなく、使用者側たる企業にも責任が生じることから、セクハラを野放しにしておくことは、その企業にとって致命傷にもなり得ます。事実を突き止め、加害者を処分するだけでなく、そこに至るまでに多くの配慮を要することに注意しましょう。