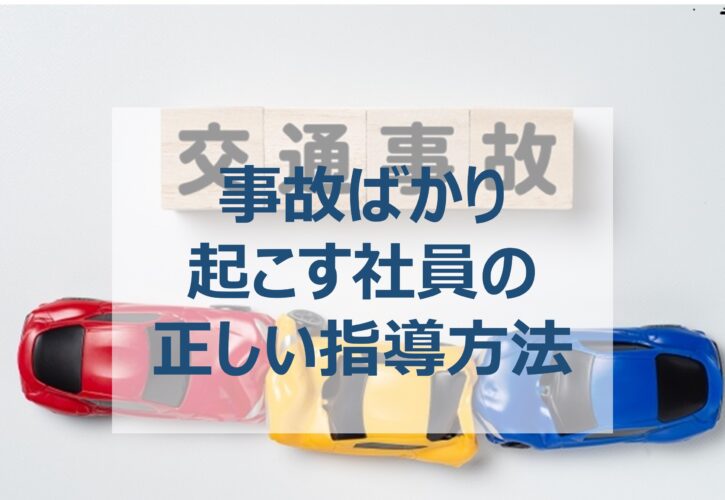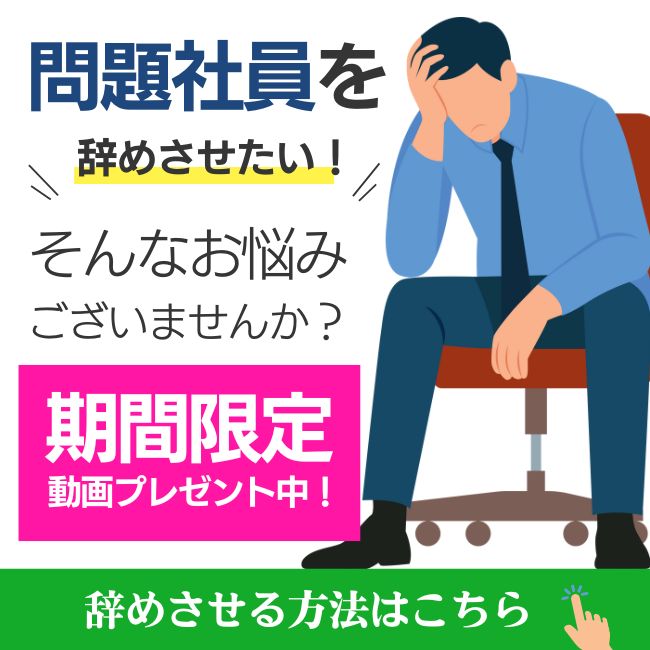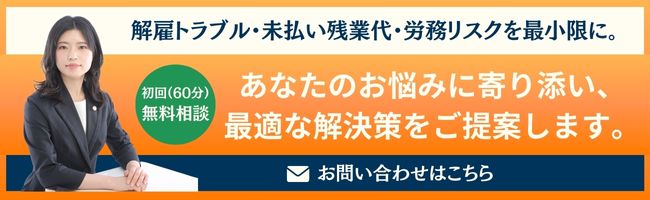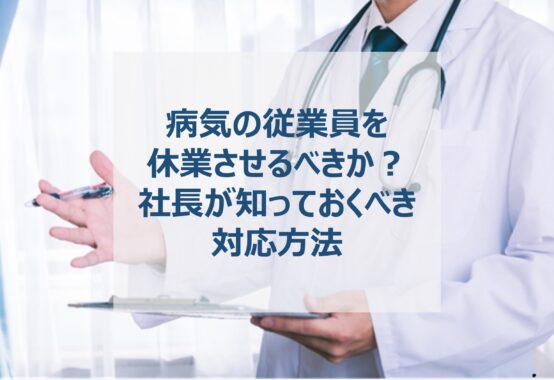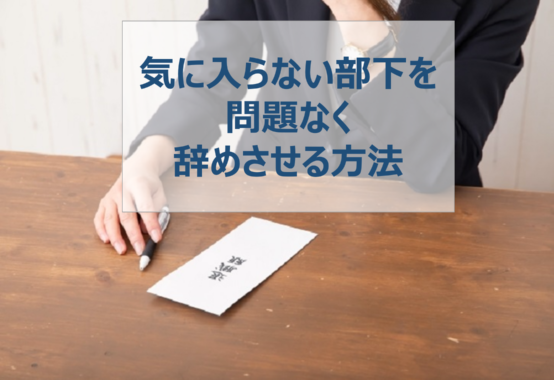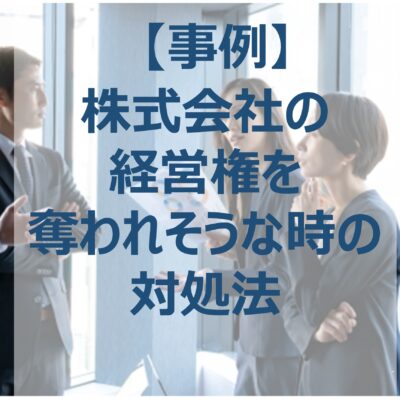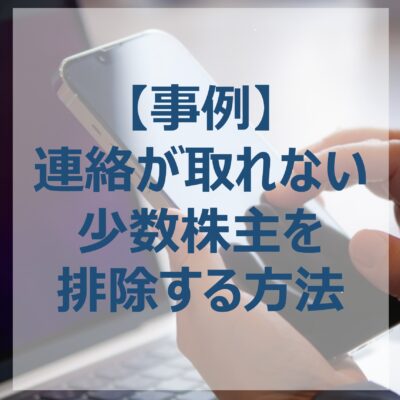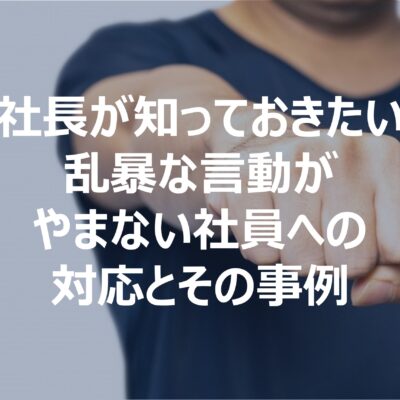会社によっては、業務中、車の運転や機械の操作、機材の移動に伴い、車両機材による事故が発生する場合があります。何度も事故を起こす問題社員に対し、会社としてどのように対処すればいいか、解説します。
1 事故原因の究明
(1)社員からの聞き取り
事故があった場合、頭ごなしに叱責するのではなく、まず冷静に事故の原因がなんだったのか、探らなければいけません。これには2つの大きな意味があります。1つは、事故の原因が現場の状態や会社の安全対策の不足、指導不足など、会社の側にあるのか、それとも不注意や体調不良など社員の側にあるのかを大別するためです。もう1つは、社員が自分の落ち度を自覚しているのかを把握するためです。
事故の原因が会社にある場合、社員を厳しく懲戒することはできず、むしろ会社の安全対策や安全教育を改善する必要があります。
また、社員が落ち度を自覚する発言をしていた場合、たとえ後に社員が言動を翻しても、大きな証拠になりますし、その他にも反省の有無や悪質性をはかるためにも参考になります。
(2)上司・同僚からの聞き取り
事故の状況を把握するためには、本人からの聞き取りだけでなく、現場に居合わせた社員や普段からの仕事ぶりや指導の内容を知っている上司、同僚からも聞き取りを行う必要があります。特に同様の事故を繰り返している場合には、以前からどのような指導をしていたのか、働き方に改善がみられたのかを聞き取りましょう。
(3)現場写真の撮影
事故があった場合には、事後的にも事故の状況を確認できるよう、現場の写真を撮るべきでしょう。警察のように徹底した現場検証をすることはできませんが、それでも様々な角度から事故の状況を写真で記録するのが望ましいです。
また、事故によって損傷や損害が生じた場合には、会社が加入している保険会社への手続も必要になりますので、事故の状況を客観的に把握できるように写真は役立ちます。
2 会社の安全対策
事故の原因の一つに、会社の安全対策の不備があった場合には、まず会社はその改善をすべきということになるので、社員への責任追及(懲戒処分や損害賠償請求)をする余地は限られることになります。
会社は、社員が安全に働けるようにする安全配慮義務がありますので、作業現場に危険物があったり、事故を起こしやすい状況にある場合には、それを防止する措置を取ったり、危険性がともなう作業では社員の技能指導や安全教育を行っていなければいけません。会社が十分な技能指導や安全教育を行わずに事故が起きてしまった場合は、社員への責任追及は難しくなります。
社員の責任が問題となるのは、社員が会社のルールを破ったことによって事故が起こった場合や、度重なる技能指導や安全教育を受けていたにもかかわらず作業習得が未熟だった場合等に限られます。
また、社員の落ち度の有無にかかわらず、業務中の事故で怪我をした場合には、労災になるので、通院費や休業手当など、労災の手続を行いましょう。
3 社員へ体系だった指導
事故の原因が究明できたら、おのずと事故を防止するための対策が見えてきますので、会社は今後の事故を防止するためにも安全対策をマニュアル化するようなイメージで、社員に対し体系だった指導をしましょう。漠然と「もっと気をつけろ」「注意して作業しろ」と言うだけではいけません。
なぜ指導が大切かというと、安全対策は第一には会社の義務だからです。会社がその義務を果たしていたのに社員のせいで事故が起こったといえて初めて、社員の責任問題になるのです。また、今まで指導していたのに、重ねて事故を起こしたということがあると、徐々に社員の責任が重くなります。そのためにも、1回1回の指導をきちんとしていたのか、ということが大切になります。
4 懲戒すべき場合
基本的には、会社の安全対策に落ち度がなかったにもかかわらず、社員の落ち度で事故が起こってしまった場合や、事故の結果が重大な場合に事故の原因となった社員への懲戒を行うべきことになります。懲戒を行うべき場合は次のようにまとめられます。
・寝不足や飲酒、注意散漫など社員の落ち度が原因の場合
・マニュアルや作業手順などに違反したことが原因の場合
・死傷者が出た場合
・損傷や損害が大きい場合
なお、懲戒手続とは別に、会社が被った金銭的な損害を社員に請求することはできるか、という求償の問題があります。これについては、全額の請求はできないというのが一般的です。なぜなら、会社は社員を使って利益をあげているのですから、その社員のミスや仕事から生じる危険にともなって損害が生じても、その損害をも会社が負うべきであるという法理論があるからです。社員の側の落ち度の大きさにもよりますが、一般的な事故であれば、損害の2~3割程度が社員に請求できる目安となります。
5 私生活での交通事故の場合
業務中の事故ではなく、私生活で交通事故などを起こした場合、懲戒の対象になるでしょうか。基本的には私生活上の事故やトラブルは懲戒の対象にはなりません。なぜなら、私生活でトラブルを起こしても、業務と直接関係しないからです。
例外的に、運転を業務としている場合、清廉さや信頼が要求される職業の場合(教師や銀行員など)、報道され会社の信用にかかわる事態となった場合、飲酒運転、死傷事故の場合には会社の業務や信用に関わる事態を招いたとして懲戒の対象となります。懲戒の対象といっても、解雇できるかというと、一概に解雇のような厳しい処分ができるわけではありません。参考として、公務員の懲戒指針をご紹介しますと、酒気帯び運転で免職か停職か減給、もっと程度の進んだ酒酔い運転で免職か停職、飲酒運転でなかったとしても死亡事故や重傷事故の場合で免職か停職か減給、それ以外の人損事故で減給または戒告とされています。
6 まとめ
社員の安全を守り、企業リスクを避けるためにも、交通事故防止対策は必須です。
日頃から交通事故を起こした場合の対応や損害金の負担など、就業規則に明記し、社員に周知徹底し、安全意識を高めるための指導を行いましょう。実際に交通事故が発生した時に適切な対応を取れるように備えておくこと、会社が損害賠償責任を負うリスクを最小限に抑えるための対策を講じておくことも大切です。