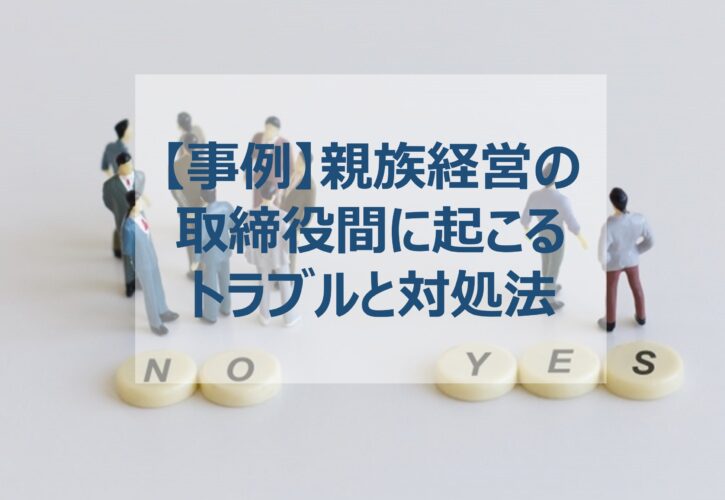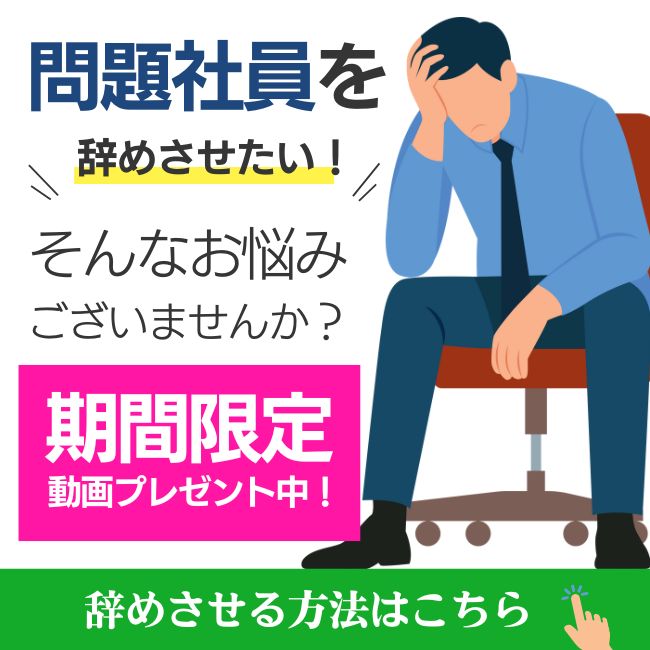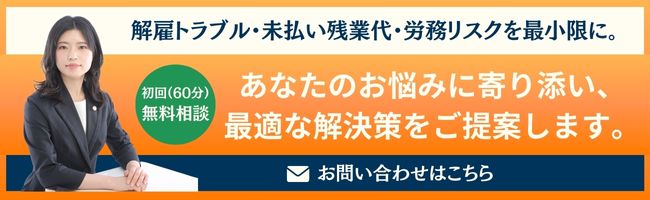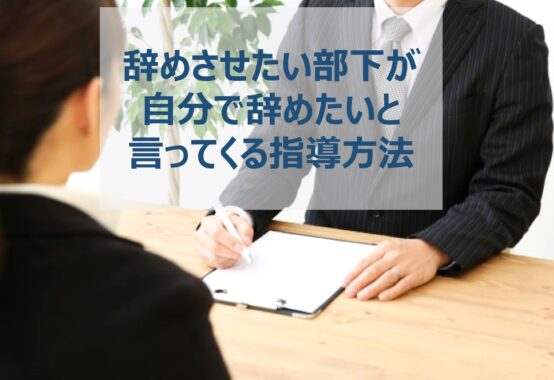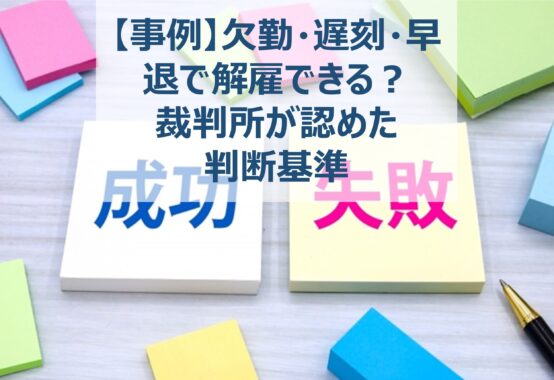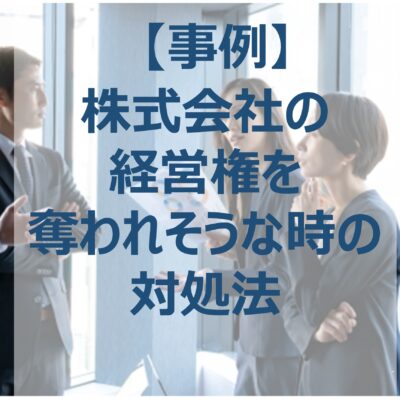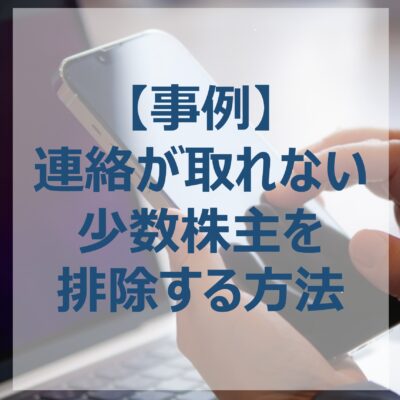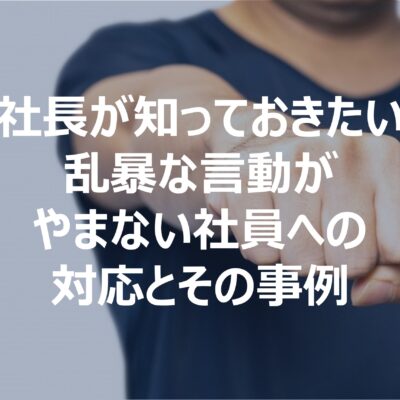中小企業では、取締役を親族同士で務めているケースや、親族ではないにしろ、近しい限られた者同士で務めていることが多くあります。知った仲だからと気が緩み、会社の適正な手続きを遺漏していたりすると、後になってからトラブルや支配権争いに発展する場合があります。今回は、親族経営でトラブルになった事例をご紹介します。
1 潜んでいた親族問題
トラブルが起きたのは、機械の製造、販売、メンテナンスを行う中規模な会社でした。現在の社長は親族経営の3代目で、取締役は社長、弟、古参の重鎮社員Aが務めており、監査役は、当時の会計責任者の社員Bが務めていました。
株式は、社長が70株、弟が20株、古参の重鎮社員Aが10株保有していました。
少し難しい言葉ですが、この会社は、取締役会設置会社といって、重要なことは取締役会を開いて決めなければいけないことになっていました。取締役会には、取締役が参加します。
本来は取締役会を開かなければいけなかったのですが、親族経営ということで「知った仲だからわかってくれるだろう」という意識が生まれてしまい、取締役会を開かないまま、会社の経営を決定することが常態化していたのです。
そんな中、取締役会を開かないまま、社長が会社の資金を自分に貸し付けてしまいました。結果的に、社長は借り入れたお金を会社に返済し終わっていたのですが、弟と会計責任者の社員Bが手を組み、社長に反旗を翻そうと、このことを問題視するようになったのです。どうも、弟は、社長を取締役の地位から退かせ、自分が社長になりたいと考えているようでした。
2 要求される法的手続
(1)取締役会事項
取締役会設置会社では、経営についての重要事項は取締役会を開いて決定しなければいけません。
会社のお金を取締役の1人に貸し付けるということも、取締役会で承認を受けなければいけないことの1つです(利益相反)。なぜなら、会社のお金が私的に流出してしまうわけですから、本来はこのようなことは、取締役会の目のある場で、取締役会の賛成を得て決定しなければならないのです。本来、取締役会の承認を得て行わなければいけないことを、それなしで行った場合どうなるか。それは、会社からその取締役に対して「貸付は無効だ」と言うことができるようになります。また、その取締役は会社の適切な手続きを守らずに貸付を受けたわけですから、過失があることになり、会社への損害賠償責任が生じます。
ところが社長は、すでに借りたお金を会社に返済し終わっていたので、貸付は無効だったと言われても無意味ですし、きちんと全額を返済して金銭的な損害が発生していませんので、損害賠償の責任も生じません。つまり、今回の事例の場合、弟や社員Bができるのは、社長の資質を問うて、社長をその座から引きずり下ろすくらいしかありません。
(2)取締役会の招集
社長の座から下ろすというのは、具体的には、代表取締役から解任するか(この場合、平取締役ではありつづけます)、取締役自体から解任するかどちらかの手続を意味します。
代表取締役から解任するには、取締役会を開き、取締役会で解任を議決することになります。一方で、取締役から解任するためには、株主総会を開き、株主総会で解任を議決しなければなりません。一般的には、取締役会の方が、株主総会よりも開催がしやすく、賛成票を集めるのも容易です。
今回の弟と社員Bも、取締役会を招集しようとする動きがありました。つまり、取締役会で社長を代表取締役から解任しようとしていたのです。ところが、ここで弟サイドには見逃していることがありました。社長を代表取締役から解任するための取締役会を開くためには、当の社長を除いた取締役の過半数の出席(定足数)が必要で、かつ、解任を議決するためには、出席した取締役の過半数の賛成が必要になるのです。
ここで、社員Bは監査役であって取締役ではないので、定足数を満たすためには、取締役である社長、弟、社員Aのうち、当事者となる社長を除いた過半数、つまり、弟と社員Aの出席が必要だったのです。古参社員のAは社長の味方でしたから、社員Aを翻意させて弟の味方にしないかぎり、弟の目論見は達成できないのです。
(3)過去の失敗の治癒
今回の場合、社長は、本来必要な取締役会の承認を得ずに会社からの貸付を受けてしまいました(利益相反)。しかし、仮に当時、取締役会に諮っていたとしたら、問題なく承認されるような事柄です。このような過去の失敗を治癒する方法はないのでしょうか。
取締役会の開催や議決に不備があった場合、その取締役会決議は無効になります。そして、無効であることは、誰からでも(取締役以外の人物であっても)、いつでも(何年経っても)主張できるとされています。つまり、ひとたび無効な決議をしてしまうと、それがずっと尾を引くことになってしまいます。
そこで、法的には、取締役会で過去に遡って承認する決議をするという方法があります。今回の事例でいうと、「あの時の会社から社長への貸付を当時に遡って承認する」という決議をするということです。ただし、実態として問題があるのに承認の決議をしてしまうと、その決議にかかわった取締役の責任問題にもなりますので、不当な承認決議にならないかどうか、慎重に判断すべきでしょう。
今回の事例では、取締役会決議をするにも、当事者である社長を除いた取締役の過半数の出席が必要になるので、結局、弟の協力がなければ、実現しない状況でした。
3 支配権争い
(1)議決権
ここまでのところで、弟も社長も、それぞれ、取締役会を開き、そこで自分の思惑通りの決議をしようと考えている状況でした。しかし、会社の取締役の人数構成からすると、お互いに、敵対する陣営の取締役の協力がなければ、取締役会を開くことができない(定足数に満たない)状況でした。
ではどうすればいいか。問題は取締役の人数と人選にあります。今いる取締役を解任したり、任期満了で退任する時に再任を認めなければ、自分に有利な人数構成に取締役会をつくりかえることが可能になるのです。
取締役の解任や再任の可否を決めるのは、株主総会です。そこで舞台は、株主総会での議決権の争いに移っていきます。
(2)株主総会の招集
株主総会というと、年に1度開かれるイメージですが、定時株主総会以外でも、臨時株主総会を開くこともできます。
株主総会を開くためには、取締役会で株主総会の開催を決定することになります。しかし今回のように取締役会の中で支配権争いがある場合には、これができなくなります。その場合、株式の100分の3以上を保有する株主は、取締役会に対して、株主総会を開催するよう請求できます。取締役会がこの請求に応じて株主総会の開催を決定すればそれでよいでしょう。仮に請求に応じない場合、手間はかかりますが、裁判所を通した手続をして株主総会を開催することもできます。
無事、株主総会が開催できた場合、過半数の議決権を有する株主が出席し(定足数)、出席者の中で過半数の議決権が賛成に回れば、取締役を解任することや、任期満了後の再任を拒否することができます。事例の会社の場合、株式は社長が70株、弟が20株、古参の重鎮社員Aが10株保有しているので、社長1人がいれば、弟を取締役から追うことができることになります。
なお、実際に取締役を解任するとなると、その取締役に職務上の落ち度がないのに、任期途中で解任した場合には、損害賠償を請求されてしまいます。そのため、任期満了後の再任を否決する方が、リスクを抑えられるといえます。
4 まとめ
今回、小規模な会社での手続の不備、支配権の争いが発端で、かなり複雑な戦略が必要になりました。「小さな会社でそこまでの戦略を講じる必要があるか」というふうに感じるかもしれませんが、会社で支配権争いが始まっている場合、相手の陣営は小さな手続の不備でも逆手に取って形勢逆転を狙ってきます。同族会社のトラブルは感情面と財産面の両軸で衝突するケースが多く、会社の規模が小さくても、法律の求める手続を実行せざるを得なくなるのです。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。