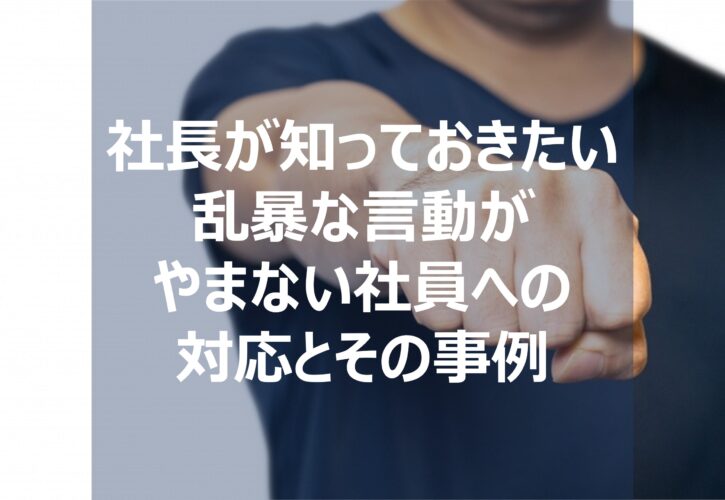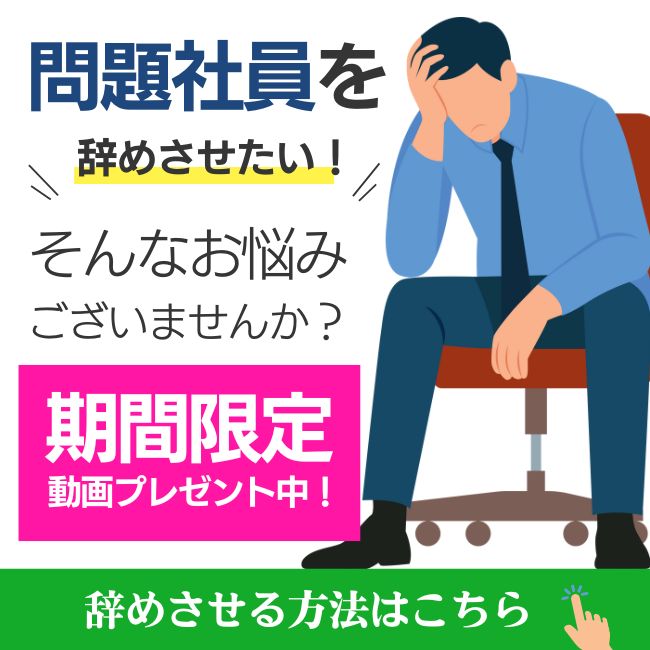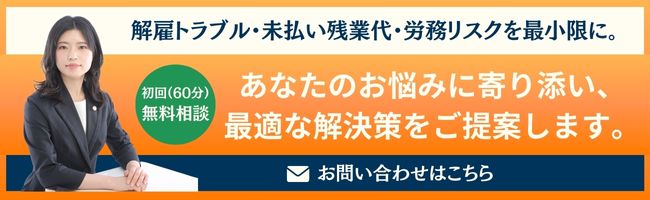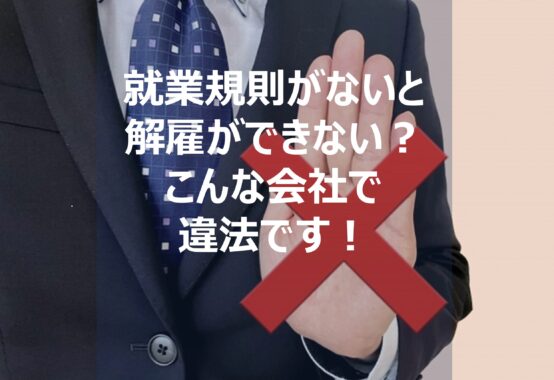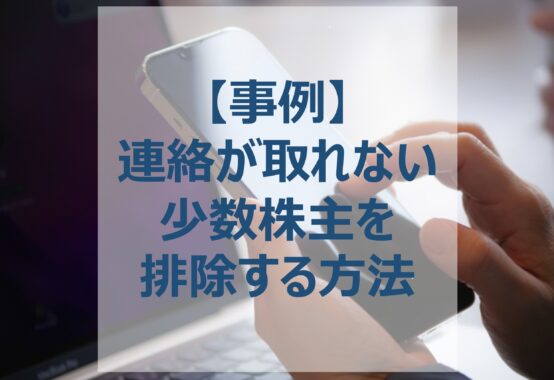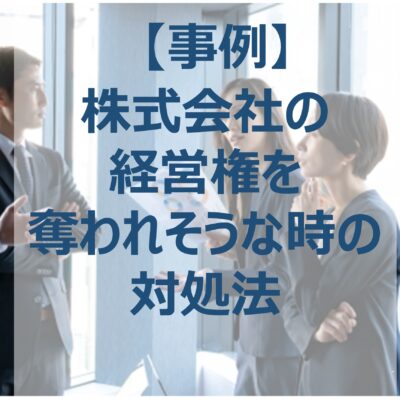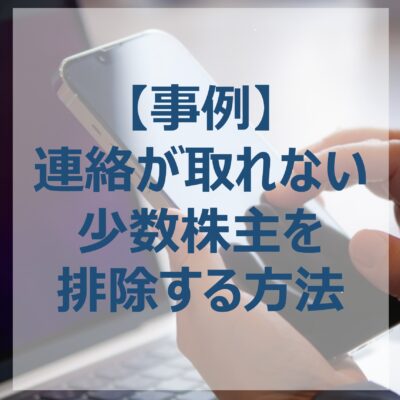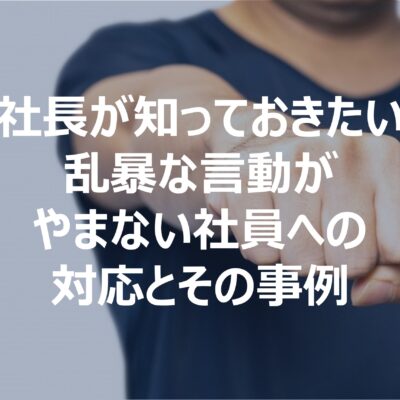言動が乱暴であったり、あからさまに上司に反発したりする社員に対して、周囲や会社は委縮してしまい、次第に手出しができなくなってしまうことがあります。このような問題社員に対して、他の社員へ悪影響を及ぼさないよう、会社は毅然とした対応をとらなければなりません。弁護士が仲介し、問題社員と合意退職に至った事例をご紹介します。
1 粗暴な社員
問題が起こった会社は正社員10人ほどの中堅の運送会社でした。正社員のうち、ドライバーは8人で、マンパワーにあまり余裕はありません。その中で社員の1人が社員の間で自分の喧嘩や悪さ自慢をするなど、周囲を威圧するような言動を行なっていました。また、その社員は業務の習熟度が低く、業務中に上司が作業のやり方などに指示を与えることが多かったのですが、上司からの指導をパワハラ呼ばわりしたり、上司に反発することも度々ありました。
社長は、問題の社員を辞めさせたいと思いつつ、その対応にあたり、上司や他の社員がその問題社員から反発やストレスを受けるのは避けたいと望んでいました。
2 目標の設定
会社としては、最終的には問題の社員に退職してもらいたいと思っていましたが、一筋縄ではいかない相手であることも承知していました。問題の社員は、同僚や後輩に乱暴な言動をしたり、上司に反発する強気な一面がある一方、このような周囲への言動や業務のやり方について、問題の社員自身、指摘されるべき点が多い状況でした。そこで、中長期的な視点で時間をかけ、その社員の問題行動に対処することにしました。
3 弁護士の対応
問題の社員は上司から仕事のやり方の指導を受けても、パワハラだと反発したり、同僚に対して「この前、街で喧嘩になって相手をボコしてやった」と悪さ自慢をして同僚が脅威に感じていたり、と周囲が指導やコミュニケーションを極力避けたいと思っている状況でした。このような状況が続くと、仕事のミスがあっても指導ができず、問題行動があってもやり過ごしてしまい、どんどん指摘しづらい空気や関係性を生んでしまいます。
そこで、問題社員とのやりとりは基本的には弁護士が行うようにしました。もちろん、日々の業務上のやりとりなど、完全には弁護士が代われない場面も多いのですが、業務上の指示に対して反発があった時に弁護士から問題のある行動であると指摘したり、問題社員からクレームがある時はすべて弁護士が聞くことにしました。
4 懲戒処分
問題の社員は、やりとりをする窓口が弁護士になってしまうと、思うように威勢を張ったり、自分の言い分を通すことができなくなり、やりづらそうにしていました。実際、その社員が「あの上司の言うことはおかしい、もっと効率的なやり方がある」と言っても、だからと言って上司からの業務上の指示に従わなくてよいことにはなりません。また、その問題社員は、会社の不正や他の社員の問題行動を訴えてくることもありましたが、調査してみると、いずれも真偽不明な事柄であったり、かなり以前の問題で既に解決済みの事柄でした。このように調査の結果を問題社員に報告すると、しばらくは同じ事柄を取り沙汰して不満や不正を訴えていましたが、それも通用しないとわかるとさらに不満を募らせていきました。
このような不満が普段の業務にも現れ、業務上の指示に対してあからさまに違反する他、業務時間中に私的行為(サボり)をするようになりました。このような事態は逃さず、懲戒処分を実施しました。懲戒処分といっても、この程度の問題行動では戒告や減給など、比較的軽い処分しか実施できません。それでも、これが重なるとさらに重い処分が待ち受けていると警告する効果はあります。問題社員からすると、自分だけ狙い撃ちで冷遇されているように思うかもしれませんが、実際に問題行動があったのですから、懲戒処分に甘んじざるを得ません。この時、懲戒処分は必要以上に重くしないこと、1つ1つ単発の問題行動に対して懲戒処分を行い、過去の問題行動をも含めて懲戒処分しないように気をつけましょう。
また、この時、他の社員にも同じような問題行動があれば、同じように懲戒しなければいけません。他の社員にはサボりや業務手順の遵守など、十分に気をつけさせましょう。
5 退職の合意
問題社員は、自分の思うように行動できず、むしろ身勝手な振舞いがもとで懲戒される状況になったことから、反発して無断欠勤をするようになりました。会社から欠勤の理由や出勤の意思を確認する書類を送り続けた結果、欠勤が1か月に及んだ時点で本人から退職の意思が示され、話し合いの上、2か月分の給与を支払うことで退職に合意しました。
6 まとめ
今回の事例は、日々の業務や会社のルールについて、問題社員が重箱の隅を突くように、会社を攻撃している状態でした。このような社員は権利意識が高いことから、会社としても不用意な発言や対応ができない状況になります。弁護士がやり取りの間に入ることにより、その問題を回避することができました。
また、権利意識の高い社員は、同時に、独自の正義を持っていることが多く、その独自ルールにしたがって行動し、結果的に社内のルール違反を犯すことが往々にしてあります。会社は慎重に行動し、会社側の落ち度をつくらず、このような機会を捉えて問題社員のルール違反に対応するようにしましょう。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。