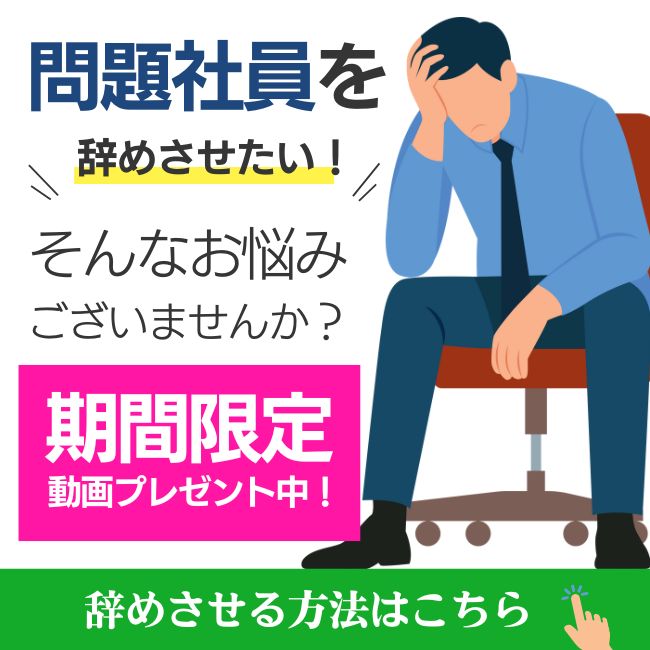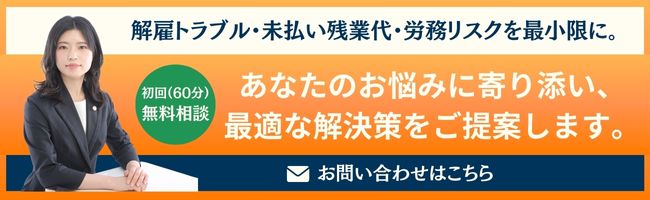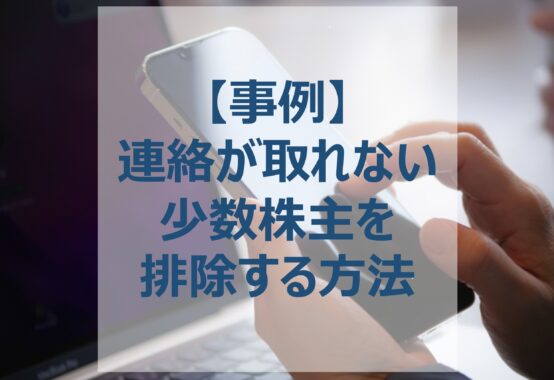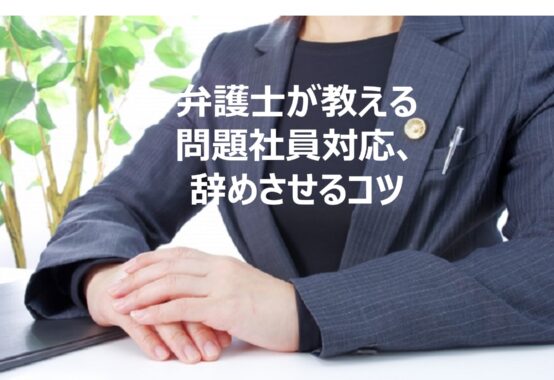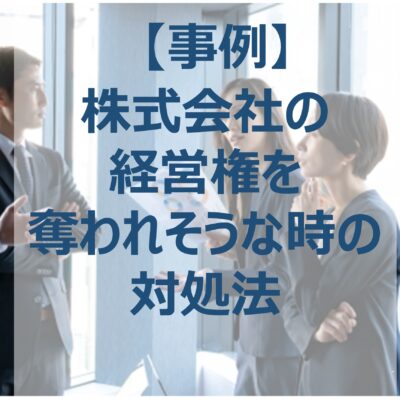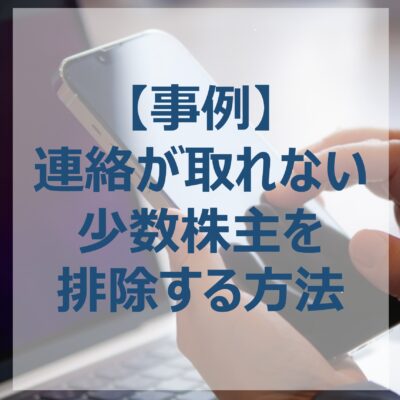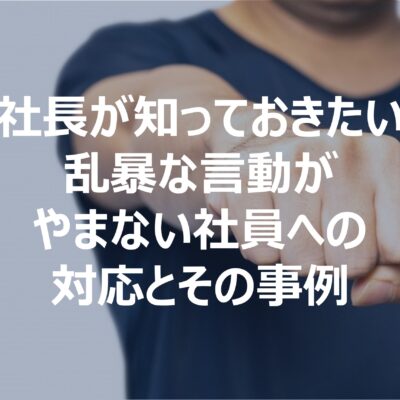社員が虚偽報告をした場合、会社としてどのように対処すべきでしょうか。虚偽報告というと、いかにも重大な違反行為という印象ですが、事の大小や事情は様々です。虚偽報告のような不正行為は、会社に大きなダメージを与える影響があるだけに、生じた場合には、早急に適切な対応をする必要があります。今回は会社が社員の虚偽報告に対応する方法を3ステップにまとめました。
1 ステップ1〜聴き取り調査
社員の虚偽報告が疑われる場合、まずは虚偽報告があったのかの確認をします。虚偽報告があったかを確認するためには、報告内容がどういうものだったか、実際の事実がどうだったのかの二つを確認しなければいけません。
まず、報告内容がどういうものだったかを確認するには、その報告が報告書やメールなど、かたちで残っている場合には、記載されている内容自体は明らかになります。ですが、報告が口頭の場合は、どういう報告だったのかを、報告者本人と報告を受けた人それぞれから聴き取りしなければいけません。
また、報告がどういうかたちで行われていたとしても、その報告をどういう意味合いでしたのか、どういうつもりでしたのか、どういう意味だと受け取ったのか、つまり言葉尻だけではわからない経緯があるかどうかや、言葉通りの意味合いで合っているのかどうかを確認しておかなければいけません。
次に、実際の事実がどうだったのかの確認ですが、これも報告者、報告の内容となっている事柄に関わっている人から聴き取りを行います。
事実関係の調査で得た証拠を元に、聴き取りを行う中で、本人の発言が二転三転する場合もあります。そのような場合は、何が本当で何が虚偽なのかの判断が難しくなってしまうので、変遷がわかるようしっかり記録に残すことが重要です。
2 ステップ2〜重大性の評価
虚偽報告の事実を確認したら、その重大性がどれほどか検討しなければいけません。虚偽の内容が軽微なものであれば、取れる措置もそれほど強力なものになりません。会社に嘘の報告をするというのは、それだけで重大な違反に思えるかもしれません。確かに、虚偽報告というのは、正常な組織運営を妨げますし、社員として誠実に業務をこなすべき義務に反するものです。ですが、嘘の内容やそれによる損害や影響にも大小様々なものがあります。虚偽報告がどれほど重大なものか、冷静に評価しなければいけません。
評価のポイントとしては、虚偽の内容、虚偽報告をした理由、加担者の有無、悪質性、虚偽報告をしたことによる影響の内容、金銭的な損害の有無などがあげられます。具体例をあげると、つぎのようになります。
虚偽の内容…遅刻の秘匿など軽微なミスを隠すものであれば、それほど重大な違反とはいえません。
虚偽報告の理由…所定時間での処理が不可能なほど業務が過重だったなど、虚偽の報告をしたことに汲むべき理由がないかも検討しましょう。
加担者の有無…複数人で組織ぐるみで虚偽報告をしていた場合、より巧妙で悪質といえます。
悪質性…虚偽報告がバレないように別の工作をしていた場合には悪質性が高いといえます。
影響…虚偽報告によって業務のやり直しや他社との取引に影響が出た場合には、より重大な事態といえます。
損害…金銭的な損害が算出できる場合には、金銭的な損害がない場合よりも重大といえます。
3 ステップ3〜処分の実施
(1)指導
虚偽報告の重大性や懲戒処分を実施するか否かにかかわらず、虚偽報告をしたことに対しては指導が必要です。
虚偽報告とは、会社組織の秩序を乱すものですから、会社で働くうえであってはならないことです。口頭ではなく、書面で「業務指導書」などを渡し、やってはいけないことだということを正式に指導しましょう。
(2)実働時間の修正・欠勤控除
虚偽報告の内容が労働時間にかかわる時は、実労働時間の修正や欠勤控除をする必要があります。例えば、就業時間中に職務を離れていたり、私用を行なっていたことが判明した場合には、その時間は労働をしていたと認められませんので、実労働時間が削減されます。また、会社の就業規則に欠勤控除の規定がある場合は、働いていなかった時間分の給与を差し引くことができます。
(3)手当の減額
会社の中には、通勤手当や家族手当、住居手当など、社員個人の生活に応じて支給される手当があります。例えば、会社の近くに引っ越してきたのにその報告をせずに、遠方からの通勤手当をもらい続けるなんてことがあてはまります。
社員がこれらにかかわる事項について虚偽報告をしていた場合は、以後の手当の支給額を修正するのはもちろんですが、既に多めに支給した手当についても返還を求めることになります。
なお、既に多めに支給した手当を返還させるために、勝手に給与から差し引いて相殺してはいけません。なぜなら、労働基準法に給与の全額払いの原則があり、会社は給与の全額を支払わなければならないので、会社が勝手に相殺することが禁止されているからです。社員ときちんと話し合い、社員から納得を得たうえで相殺することはできますが(相殺合意)、本当に社員が納得したかどうか、相殺したことで月給がかなり少なくなってしまい社員の生活を圧迫することにならないかどうか、法的なハードルが高いので、おすすめできる方法ではありません。給与との相殺はせずに、別個に過払い分を社員から返還支払いをしてもらうのが安全です。
(4)採用取消し
採用の時に報告していた経歴に虚偽があった場合の対応には要注意です。一般的な感覚ですと、採用時に嘘をついていたなら、採用の前提が崩れるから、即採用を取り消せると思われがちです。ですが、法的には、採用取り消しにできる場合はかなり限られています。
まず、虚偽の内容が、採用時には知ることができず、採用後に発覚したものでなければいけません。
そして次に、その事項について会社が採用時に質問をするなどして採用選考の要素にしていなければいけません。これはつまり、元々採用の時に明確には気にかけていなかった事項について、後から引き合いにだして採用を取り消すことはできないということです。採用のための前提条件となるような重要な事項なのであれば、採用の時に会社の側からきちんと質問しておくはずだろう、という発想なのです。
(5)懲戒
虚偽報告をした社員に対し、懲戒処分を行うこともできます。その際注意しなければならないのは、検討した虚偽報告の重大性をもとに、重みに見合った処分を実施するということです。不正行為とそれに対する制裁としての懲戒処分の重さが釣り合っていなければなりません。虚偽報告が軽微なものであり、汲むべき理由や会社の落ち度がある場合には、懲戒を実施せずに指導にとどめる場合もあります。
懲戒をする場合は、虚偽報告の重大性を慎重に判断し、就業規則の懲戒事由にあてはまるかを検討しましょう。かんたんに解雇することはできない例として、こんな判例があります。
教師が修学旅行中に職務を離れてゴルフのプレーに行き、発覚した際に学校に対し、プレー時間や費用負担について虚偽報告をした事案で、この教師に対する懲戒解雇は無効とされた。職務中のゴルフプレーは教師としてあるまじき行為ではあるが、解雇に値するほどの重大な違反行為ではなく、虚偽報告についても少しでも自分を庇おうとすることが人間の情であることからすると、虚偽報告をしたことを解雇が有効になるほど殊更に重く評価することはできないとした(平成5年9月29日大阪地裁決定 村上学園事件)。
4 まとめ
虚偽報告とは、いかにも許し難いことのように思いますが、対応を冷静に判断しなければ、逆に会社の取った措置に落ち度がうまれてしまいます。対応していく上で、証拠の確保が重要になりますが、虚偽報告をするのにも、社員の側に言い出しづらい心理や事情があるということを踏まえて重大性を判断しましょう。