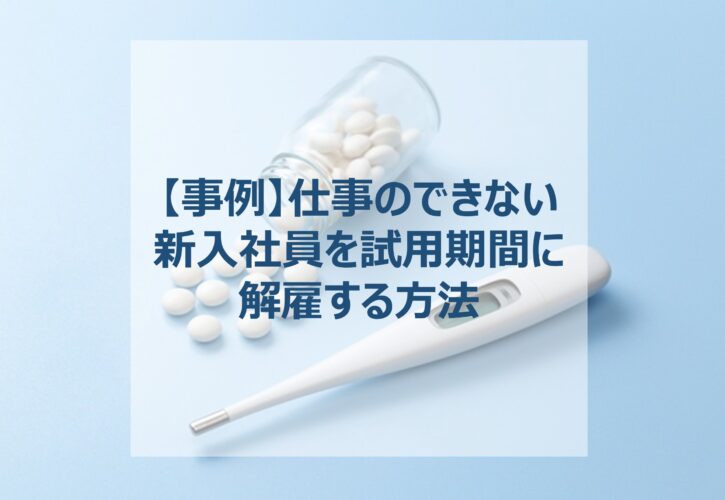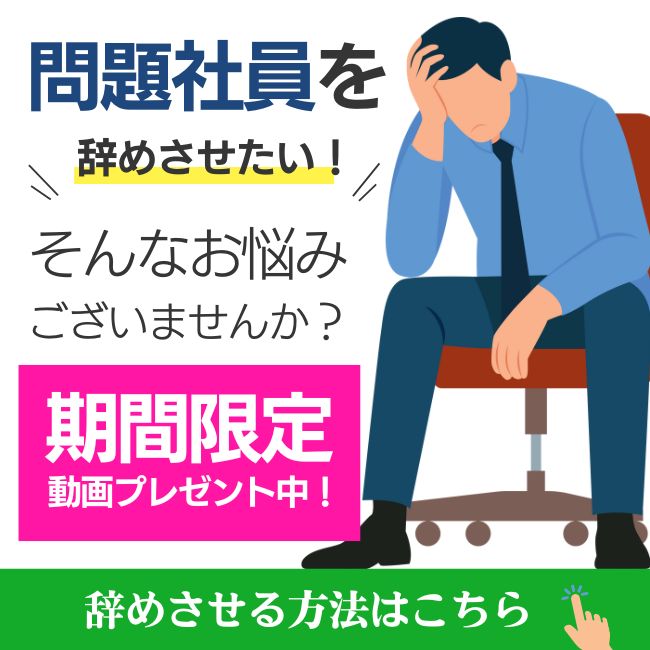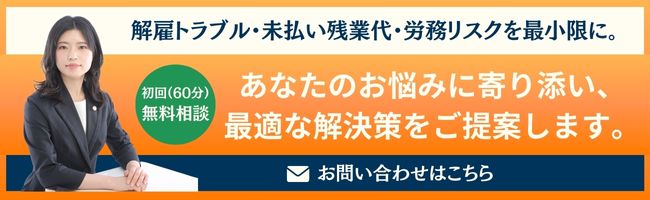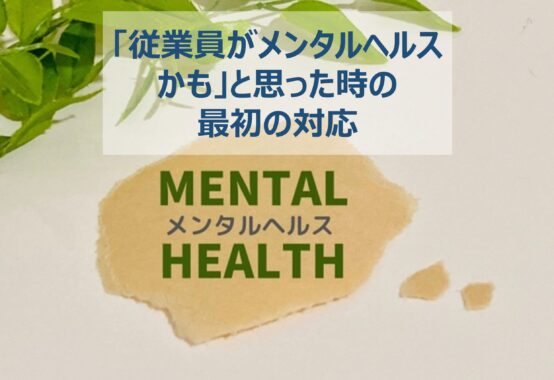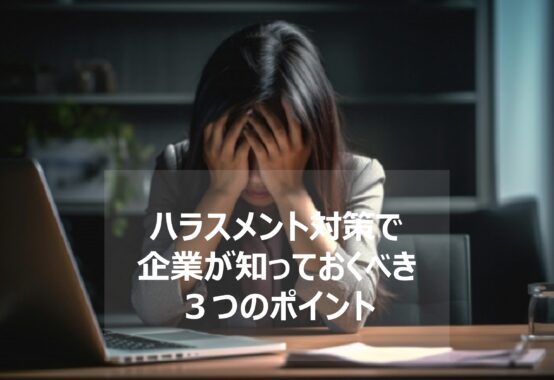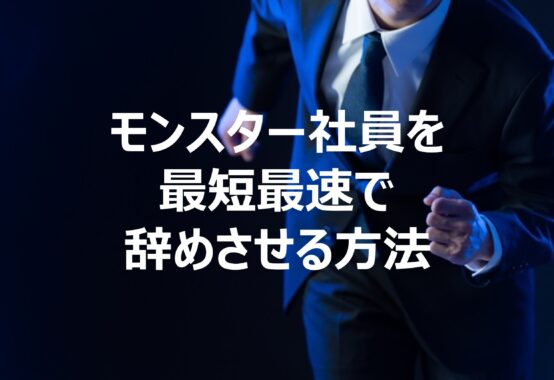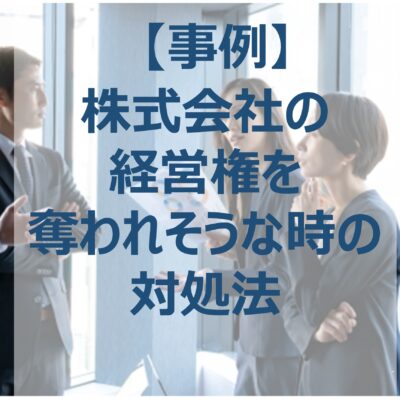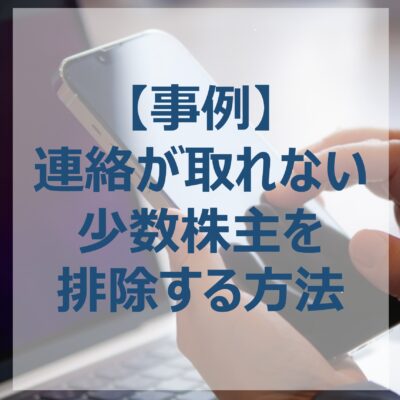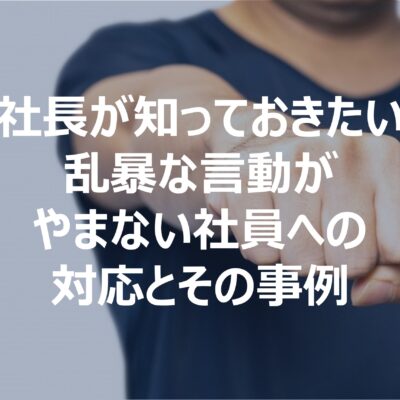大型連休が終わり、日常生活が戻る時期になると「5月病」という言葉があるとおり、新しい仕事や職場への気持ちが途切れ、新入社員が会社になじめなかったり、仕事についていけずに退職してしまうことがあります。今回はそんな事例の対処方法をご紹介します。
1 空回りする新入社員
問題が起こったのは、正社員2人、パート社員3人の小規模な音楽企画会社でした。新たに採用したパート社員の1人がどうもあまり仕事ができませんでした。本人はそれを自覚してか、挽回しようと自分で作業を抱え込んだり、不必要な残業をしたりするのですが、それが返って会社の業務を妨げている状況でした。社長はそれとなく口頭で指導しながらも、明確なダメ出しや書面に残るかたちでの指導はしていませんでした。
問題の新入社員は、体調不良を理由に欠勤をする日が月に何日か目立つようになり、ついには適応障害の診断書を持ってきて、1か月以上の療養が必要だとして長期欠勤を始めました。
2 方針の決定
(1)本採用拒否の法理
社長としては、パート社員で、しかも入ったばかりの社員が満足に仕事をこなす能力もなく、しかも欠勤を始めたので、これを機に辞めてもらいたいと考えていました。
たしかに、問題の社員は入社間もなく、試用期間の時期でしたから、体調の問題で勤務に耐えないことを理由に、本採用を拒否することは可能な状況でした。しかしながら、試用期間中といっても、本採用を拒否することは、法的には解雇とほぼ同じ重みを持ちます。本採用拒否は、解雇よりは多少容易にできるとされていますが、それでも法的に不備のないように万全を期さなければいけません。
この事例では、問題の新入社員には、能力不足の問題と体調不良の問題の2つがありましたので、その2つそれぞれについて、本採用拒否の理由となるかどうか検討しました。その点で、問題の新入社員の能力不足については、問題を起こした明確な証拠や会社が指導を繰り返していたという明確な証拠がなかったため、能力不足を中心的な理由として本採用を拒否することは難しい状況でした。そのため、体調不良で業務に耐えないことを理由に本採用拒否をすることが有力になりました。
(2)新入社員の心理
また一方で、問題の新入社員のこれまでの態度からして、出来ないことや落ち度を指摘されると、それを否定しようと躍起になってしまう(作業の抱え込みや不要な残業をしていた)ことが懸念され、能力不足にしろ、体調不良にしろ、仕事ができないから辞めろという強硬な態度で臨むと紛争化する危険がありました。そのため、問題の新入社員の心情に配慮した対応が必要だと予想されました。
そこで会社としては、体調第一で欠勤を容認しつつ、長期欠勤で働けていないことが新入社員本人にとっても受け入れざるを得ない状況をつくり、体調不良で業務に耐えないことを主な理由として試用期間満了時に本採用をしないという方針を打ち出しました。
(3)解雇予告
ちなみに、試用期間が14日以上経過している場合には、本採用拒否をする時は解雇予告手当が必要になります。一般的に、企業の試用期間は3か月程度ありますから、本採用拒否をしようとする場合にはすでに14日が経過し、解雇予告手当が必要になることが多いでしょう。その場合、試用期間満了の30日前までの間に本採用拒否の通知をするか、足りない日数分の解雇予告手当を支払う必要があります。
3 実践した対応方法
問題の新入社員は、すでに適応障害の診断書を提出して欠勤を開始している状態でしたので、ひとまずはその欠勤を認めることにしました。ただし、入社から間もなく、会社の休職制度の適用対象外だったため、単なる欠勤を続けている状態になります。欠勤を続けていると、当然、給料は欠勤の日数分控除されます。
会社としては、定期的に体調確認の連絡を行い、復職可能な目処がついたかどうか確認しました。そのうちに日数が経過していき、試用期間の満了時期が迫ってきます。試用期間満了の30日前までのタイミングで「本採用について検討するため会社で面談したい」と連絡しましたが、体調不良を理由に問題の新入社員は面談を欠席しました。
そこで、書面で現在の検討状況を本人に知らせることにしました。その書面にも、問題の新入社員の心理を読んで、能力不足で仕事ができないということを一番最初に書くのではなく、体調面の問題で出勤できていないことを冒頭に書き、そのことが主だった理由で本採用をしない見込みであることを伝えました。
4 退職の実現
その後、試用期間満了30日になる前に本採用拒否の通知を送る予定でしたが、それよりも前に問題の新入社員から「自己都合で退職したい」という連絡があったため、自己都合退職と明記した退職合意書を送り、サインをして送り返してもらいました。
5 まとめ
近年、新入社員の早期離職が増えています。中には今回の事例のように、自分の能力不足や会社とのミスマッチを感じながら、それを直接の理由として辞めるとは言い出しづらく、適用障害などのメンタル系の診断書を持ってきて、欠勤を開始する場合が多くあります。経営者としては復職しても、会社が望むような仕事をこなせないことが予想される現況では、生涯人件費の投資リスクを回避する方策を採ることは至上課題でしょう。しかし、診断書を持ってきている以上は、仮病とは扱わず、きちんと体調不良と扱ったうえで、「業務に耐える心身の状態にない」ということを理由に退職へ進むようにしましょう。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。