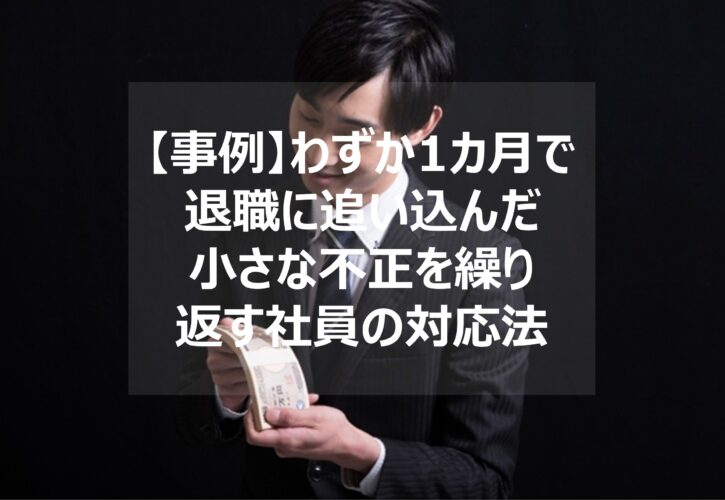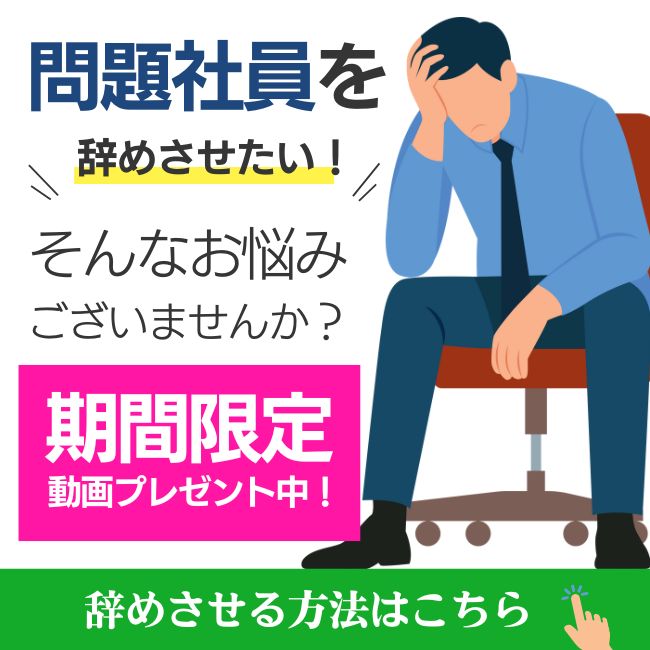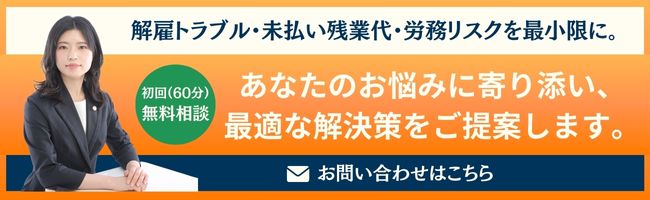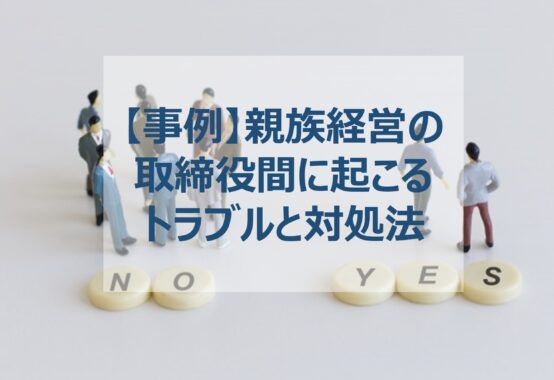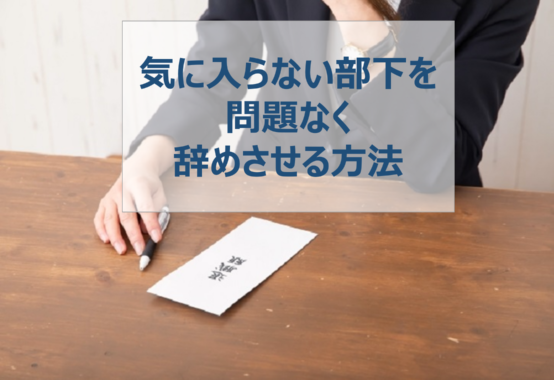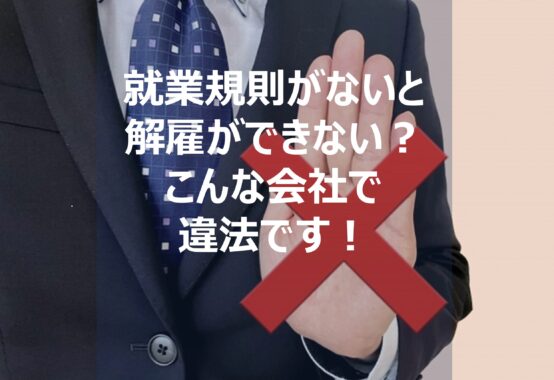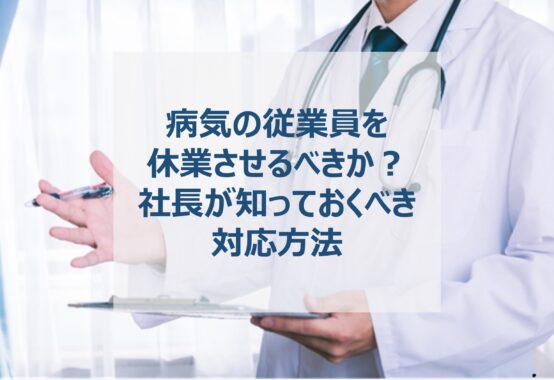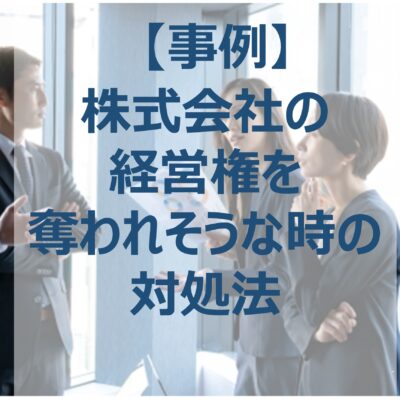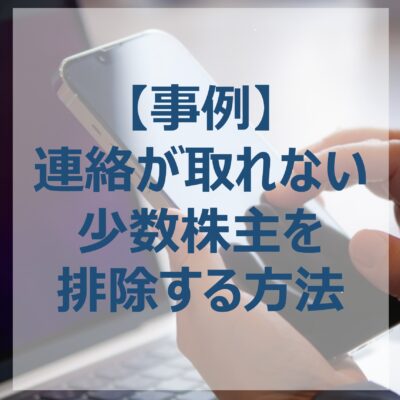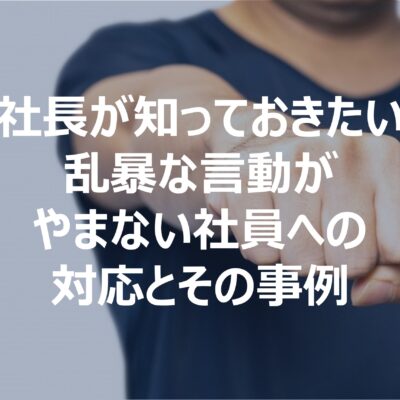社内で社員の不正が発覚した場合、どのように対処すればいいでしょうか? もちろん、不正を行ったのですから、懲戒処分など、なんらかのペナルティは必要でしょう。ですが、解雇できるか、というと、話は別です。今回は、解雇できるかは悩ましいレベルの不正行為を行なっていた事例で、どのようにして問題社員と合意退職に至り、スピード解決できたかをご紹介します。
1 小さな不正を繰り返す社員
トラブルが起こったのは、資格試験予備校を営む会社でした。創業10年ほどで堅調に生徒数を伸ばし、教室を2箇所構えていました。正社員は2人で、非常勤の講師やアルバイトも5人ほどいました。問題の社員は正社員の1人で、教室の1つを任せていましたが、社長と年齢も近いこともあり、いつしか独断で教室運営を行うようになっていました。本社のルールを無視して教室運営を行うので、教室運営が非効率になっていたうえ、社長は、その社員が本社には見えないかたちで不正を行っているのではないかと疑念を抱くようになっていました。
社長が本社ルールに合わせるよう度々指導していましたが、しばらくするとまた独自ルールに戻してしまったり、会社のやり方への批判を交えて「忙しくて対応できない」と反発したりしました。困った社長が監視の目を強めると、問題の社員には他にも不正行為があることが発覚しました。社長は長年の我慢が限界に達し、すぐにでも解雇することを望んでいました。
2 不正の重さと解雇
社員が不正を行なっていたとしても、すべての場合で解雇できるわけではありません。解雇されても仕方がないといえるほど、解雇に見合った重大な不正でなければいけません。解雇されるのに見合った理由があることを、解雇の客観的合理的理由といいます。
例えば、会社のルールで定めた方法で業務を行わないというだけでは、解雇の理由としては万全ではありません。そのような場合、まずは会社がルールどおり業務を行うように指導を徹底すべきで、すぐに解雇できるわけではないのです。
一方で、金銭を直接取り扱う立場にある社員が横領をしたりすると、業務の根幹に関わる不正とみて、解雇が認められやすくなります。ただしこの場合も、過去に会社が同様の事例に寛大な処分をしていたとか、金額が少なく、弁償もされ、その他にも社員の側に汲むべき事情があったりすると、解雇が否定される要素となるので、判断は慎重に行わなければいけません。
3 不正対応への落とし穴
不正が発覚したとしても、会社側に思わぬ不備があり、対処ができないこともあります。
(1)就業規則の不存在
不正行為に対してまず思いつくのは、懲戒処分を課すことでしょう。しかし、懲戒処分を行うためには、不正行為が行われる以前から会社に就業規則があり、その就業規則に懲戒に関する規定がなければいけません。懲戒処分というのは一種の罰ですから、罰を課す前の時点で、どんな行為をしたら罰されるのか、どんな罰があるのか、明確に規定されて周知する必要があります(周知とは、実際に知っていることではなく、いつでも知れる状態にあることをいいます)。
いくら不正行為の証拠があったとしても、就業規則がなければ、懲戒処分や懲戒解雇は絶対にできません。事例の会社では、会社が小規模なこともあり、就業規則を作っておらず、懲戒処分、懲戒解雇ができない状態でした。
(2)長年の放置
不正行為があったとしても、そのことを知りつつ長年放置してきた場合には、不正行為に対処する際のマイナス要素となります。
事例の会社でも、いつかのために、とその社員の問題行動を2〜3年にわたり記録していました。しかし、問題行動を知りながら指摘したり指導したりせず放置してきたということは、会社はその行動を問題視せず、許してきたということにほかなりません。もちろん、許すつもりはなかったのでしょうが、客観的に評価すると、その問題行動を問題としてとりあげなくてもよいと判断したということになってしまいます。それを後から取り沙汰して社員に対して不利益な処分を行うというのはできないのです。
問題行動の証拠を長年ためて、最後に1度、大きな処分(解雇)をする、ということはできないので注意しましょう。
4 不正の調査
事例のケースでは、懲戒処分もできなければ、解雇も難しい状況でした。とはいえ、問題の社員に退職または反省を促すうえで、不正行為が鍵を握ることには変わりありません。そこで、どのような不正行為があるのか、調査を行うことにしました。
(1)客観的な証拠の収集
不正行為を指摘するうえで、客観的な証拠は必要不可欠です。指摘された社員は不正行為を否定して言い逃れをする可能性が高いですから、言い逃れのできない客観的な証拠を用意しておく必要があります。また、社員が不正を否定している状況でなんらかの対処を行うことになるのですから、事後的にもし裁判などに訴えられても会社が勝てるくらいの証拠の備えは必要です。
事例の会社では、防犯カメラの記録や帳簿などから、営業時間外に一部の生徒に特別授業を行なっていたり、そのことを隠すために二重の時間割を作成し、嘘の時間割を本社に提出していたこと、生徒から徴収した教材費の一部(数万円程度)を本社に報告せずに横領していることが判明しました。
(2)重大度合いの評価
不正行為といってもその重大さはさまざまです。重大さに見合った処分をくださなければいけません。
事例の会社の場合、営業時間外に授業をしたりそれを隠す工作をしたことは、教室運営を任せることができなくなるほど重大な行為といえるでしょう。ですが、それで退職まで迫れるかというと、万全ではありません。教室運営の責任者から退任させることと、退職させて社員であること自体を否定することは、重みが段違いなのです。時間外営業をしていたとしても、その分、生徒の1月あたりの授業コマ数は消費されていたので、会社に実害や損失が出ていたとまではいえない状況でした。また、横領をしていたことは、退職を迫れるだけの重大さがありましたが、金額がわずかであったことから、問題社員が弁償を申し出た場合には退職を押し切れるかどうか危ういといえます。
(3)問題社員の心理
不正行為や社員の落ち度を指摘する場合、その社員にとって何が一番、身に覚えのあることか、受け入れやすいことかを考えるのも大切です。これは、必ずしも不正の重大性と一致しません。それほど重大でない問題行動であったとしても、話し合いの際には、社員の心理を反省や退職方向に動かすために、社員が一番気にするであろうことや受け入れるだろうことから指摘することが有効です。
事例の会社の場合、その社員にはこれまで何度も本社のルールにしたがって時間割を管理するように指摘してきた経緯があったので、その違反を一番自覚しているだろうと判断し、営業時間外に授業を行なっていたことを最初に指摘することにしました。
5 合意退職へのアプローチ
事例の会社では、懲戒処分や解雇が難しい状況でした。そこで、問題の社員と合意退職に至ることを目指すことにしました。もちろん、退職に合意しないこともあり得るので、その後に敵対的な関係にならないよう、退職を強要しているように捉えられる発言はしないようにしました。また、退職しないのであれば会社は今後どのように処遇するつもりなのかを用意しておきました。
実際に問題社員と面談を行い、証拠を面前に示しながら、本社に秘密で授業を行なっていたことを指摘しました。この時点で問題社員は観念した様子に変わっていました。教材費の横領についても証拠を示した後、「これからどうしていくのか」「このようなことがわかった以上、今までどおりに処遇することはできない」と伝えました。この時、会社からは「辞めろ」とか「辞めてもらわなければいけない」というように解雇や退職を連想させる言葉は使いませんでした。すると、問題社員の方から「辞めます」という言葉があり、その場で退職の合意書を作成することになりました。
この時、社員から退職の意向が示されなければ、今後は教室運営を任せるのは辞めて、本社で社長の目の届くもとで働くこと、その際には本社ルールを遵守するよう誓約書を取ることなどを用意していました。結果的に退職の意思が示されたので、この代替策は使わずに済みました。
そして、急遽、退職の合意が成立することになったので、用意していた退職の合意書に必要事項を記載してもらいました。後で翻意されたり、思い違いを主張されないよう、何度も退職の意思を口頭で確認し、退職の時期やそれまでの処遇について、社員の要望をよく聞いて退職合意書に反映させました。
また、社長は、その社員が、教室の近くで別の予備校を立ち上げて競業したり、生徒にアプローチして生徒を引き連れて独立・競業することも懸念していました。そのため、退職時には競業についてもルールを定め、合意書にすることができました。
6 まとめ
この事例は、懲戒処分もできなければ、解雇も難しい状況でありながら、結果的に、退職を認めさせるための金銭(コスト)を払うことなく、しかも、依頼を受けてから1か月程度でスピード解決できました。不正発覚という、社員にとっては不利な状況もあって、競業についての合意もすることができました。ただし、その状況につけこんで強要するかたちで退職や退職の条件を合意してはいけません。会社の利益を優先しすぎず、社員が合点できる妥協点を見つけましょう。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。