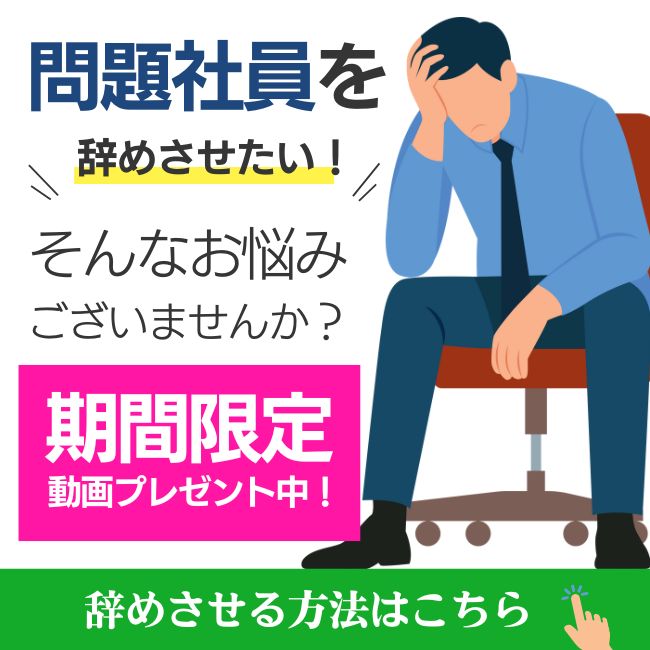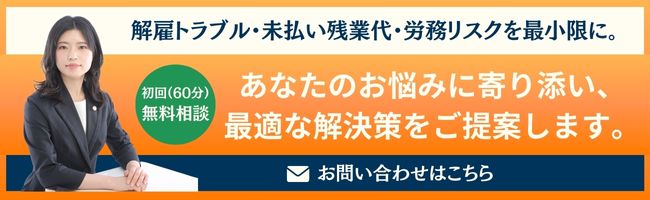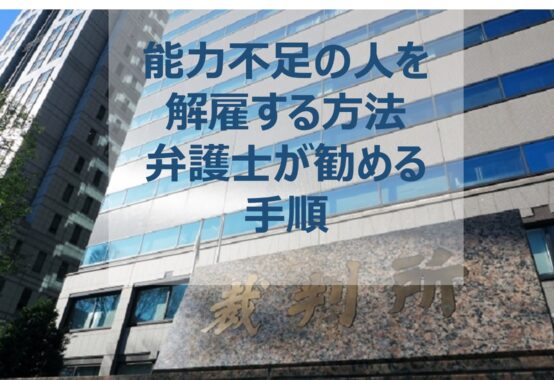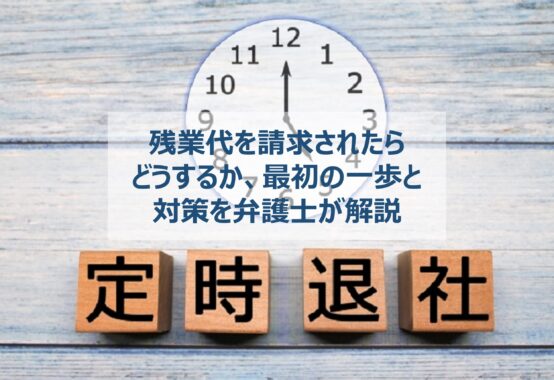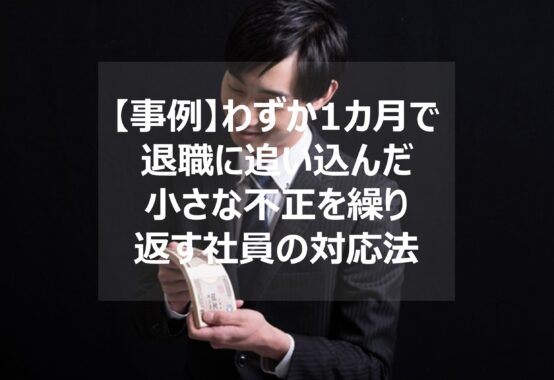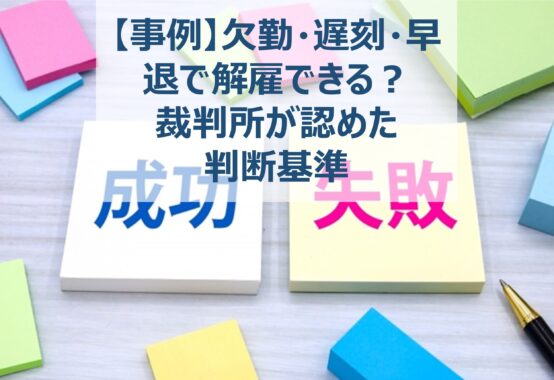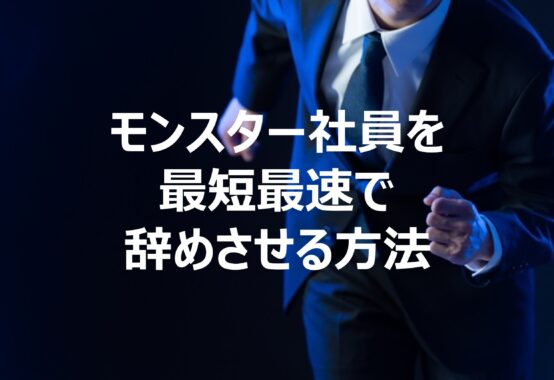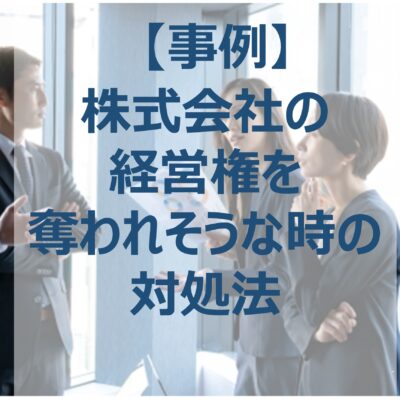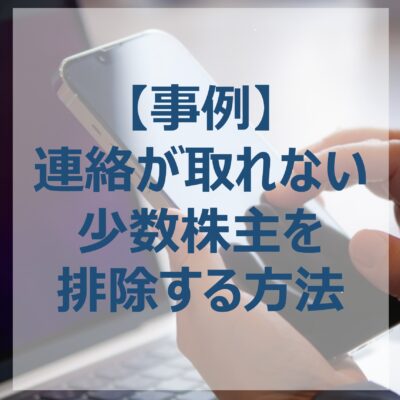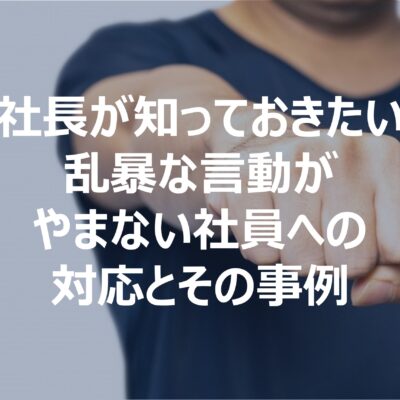セクシャルハラスメントの略称である「セクハラ」。職場で発生する性的な嫌がらせのことで、厚生労働省の指針では、会社にセクハラの防止措置をとることを義務づけています。職場でセクハラが行われているにもかかわらず、会社が適切な対応をとらずにいると、社員の士気を低下させ、休職者や退職者が発生する恐れがあります。無意識に誤ったセクハラ対応をしないよう、今回は、経営者にありがちなセクハラ処分の5つの失敗について解説します。
1 相談体制の準備不足
セクハラ被害にあった社員がセクハラを訴えようとしても、会社の相談体制が整っていないと、被害が埋もれてしまったり、それによって事態が深刻化する場合があります。
法的には、すべての企業にパワハラの相談窓口を設けることが義務付けられていますが、セクハラの相談窓口については義務付けられていません。ただし、これはセクハラの相談窓口はいらないということではなく、企業には相談の中身を限定せず、ハラスメントに関する横断的な窓口を設置すべきと推奨されているのです。
相談窓口といっても、大それたものを想像すると及び腰になってしまい、余計に設置から遠のいてしまいます。最低限、最初に相談の受け手になる担当者を決めること、そしてその担当者が誰に対し報告をし、誰が次の対応を決定するのかを決めておきましょう。最初の相談窓口だけを決めておいても、その後の処理手順を決めておかないと、相談されたセクハラ事案が放置されてしまいかねません。せっかく相談をしたのに、会社に対応されずに放置されてしまうと、被害者は会社に対しても不信感や敵対心を抱いてしまい、事態が混乱してしまうのです。相談窓口を設けると同時に、その後の対応手順についても決めておきましょう。
2 プライバシーの配慮不足
セクハラがあったかを調査する時、被害者、加害者、場合によっては目撃者や周囲の人間からの聞き取りが必要になります。ここで注意すべきなのは、被害者、加害者、双方のプライバシーに十分配慮することです。
セクハラ被害に遭ったということは個人としての尊厳を傷つけられるもので、被害者としては決して他人には知られたくない情報です。同じように、セクハラの加害者とされていることは、加害者が他人に知られたくないと思う情報でもあります。聞き取りを行う時は個室で行うこと、聞き取りの対象者以外に情報が漏れないようにすること、聞き取り対象者を厳選すること、被害者加害者以外への事態の説明の仕方には十分に気をつけましょう。
また、被害者の希望に配慮することは必須なことと心得ましょう。被害者がセクハラ被害を相談窓口に持ち込んだとしても、必ずしもセクハラ問題としてほしいとは限りません。穏便に部署異動をさせてほしいというだけの場合もあるでしょう。加害者への聞き取り調査を望まない場合もあります。被害者がどこまでの対応を望んでいるのか、調査を実施する場合にどこまでの事実を聞き取り対象者に伝えていいのか、きちんと確認しましょう。
3 個人の問題に矮小化
セクハラ問題が起こった時に、それを社員個人間のトラブルだと考えて、当事者同士で解決しなさい、という対処をすることは絶対にいけません。
セクハラ問題は、必ずしも業務時間中だけではなく、業務時間外でも起こります。しつこく食事に誘われたり、その際に性的な言動を受けたりといったパターンもあるのです。業務時間外であってもただの人間関係のトラブルと捉えてはいけません。なぜなら、加害者がいる環境で変わらず被害者を働かせ続けることが、会社の安全配慮義務違反にもなるからです。
そもそも、個人同士で直接解決できない状況に精神的に追い詰められているから、会社に相談しているのです。個人の問題だと矮小化せず、セクハラ問題の対応の責任は会社にあるという意識をもって、対応にあたりましょう。
4 社長個人の価値判断
社長、そして社長に限らず、人事に権限のある社員が個人の価値観でセクハラ問題を判断しないことが大切です。セクハラはいまや社員個人同士の問題ではなく、会社で安全に働けるかという会社の就業環境の問題です。一人で判断するのではなく、チームで慎重に検討しましょう。
これは実際にあった事案ですが、社員が飲み会の席で社長にセクハラの相談をしました。ですが、社長は、当事者の社員同士の普段の働きぶりを見ていたり、加害者の社員の人柄を知っていたり、相談されたのが飲み会の席だったということもあり、「仲良く働いてほしい」「加害者も君と打ち解けたいだけだと思う」などと言ってしまったのです。社長としては、二人の仲を穏便に済ませようとしただけかもしれませんが、これがきっかけで、被害を訴えた社員は、会社に言ってもまともに対応してくれないと思い詰めるようになり、ついには訴訟に発展してしまいました。セクハラの相談があった時にはその場で事を収めるようとするのは厳禁です。
5 時代に合わない判断
セクハラがあったか否かを判断する時、時代に合ったセクハラの定義を対応にあたるチームで共有することはとても大切です。
「肩を叩いたくらい」「頭を撫でたくらい」「何度か食事に誘ったくらい」これらは一昔前までは、そんなことではセクハラにならないと考えられていましたが、今はそうではありません。「性的な内容の発言」や「性的な行動」のいずれかにあたれば、セクハラがあったと認定されるので、時代の変化に対応しなければいけません。懲戒や損害賠償の対象になるかは微妙ですが、少なくとも厳重注意は必要な言動といえるでしょう。
また、世間一般ではセクハラになる言動だと理解していても、顔を知った社員同士、「あの人に対してだったらここまでやっても大丈夫だろう」ということが起こりがちです。ですが、世間一般でセクハラに該当し、実際にやられた側が嫌だったと訴えている以上、それは間違いなくセクハラです。「あの人との関係だったら許される」という言い訳は何の意味もありません。会社はそのことを冷静に判断しましょう。
日頃のニュースや書籍の情報から、今の時代、何がセクハラに当たるのか正確に把握することは大切です。また、普段から社内でセクハラ研修を行ったり、ポスターで啓発するなどすれば、社員の間に「こういうことをやったらセクハラになる」という意識が芽生え、セクハラ防止にも役立ちます。
6 まとめ
セクハラによるトラブルは対応によって収束に向かう場合もあれば、拡大する恐れもあります。しかし、セクハラ対応の失敗は、知識を持ってさえいればかんたんに防げることです。まずはセクハラに対する会社の責任やスタンスをきちんと理解しましょう。