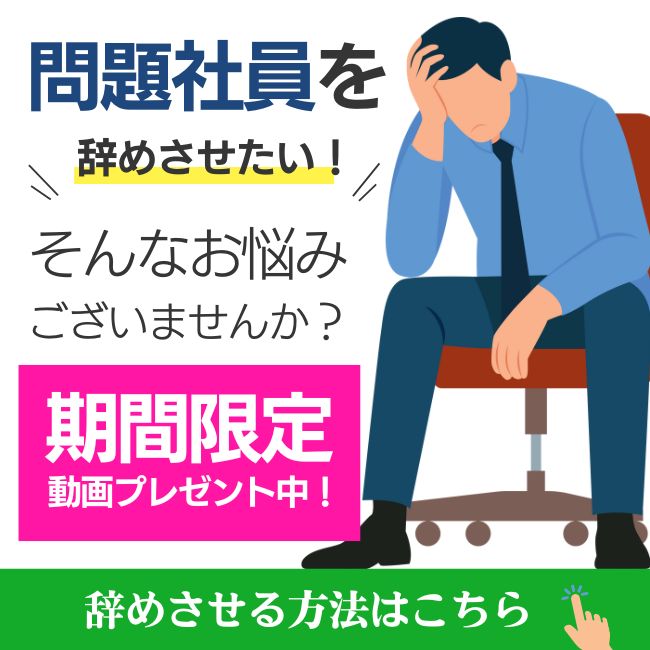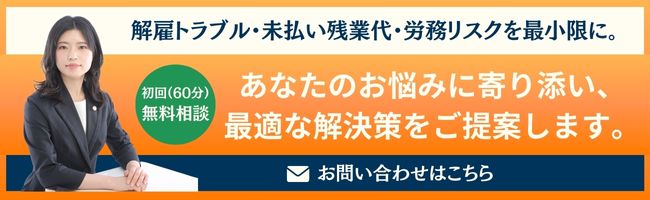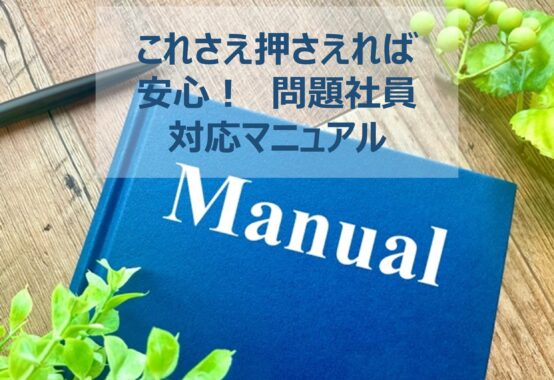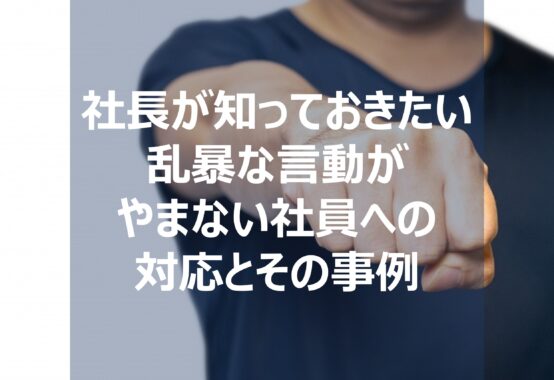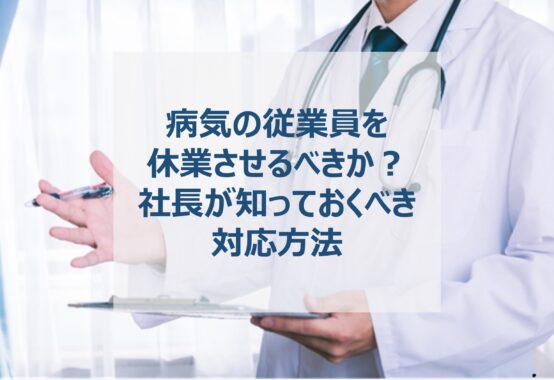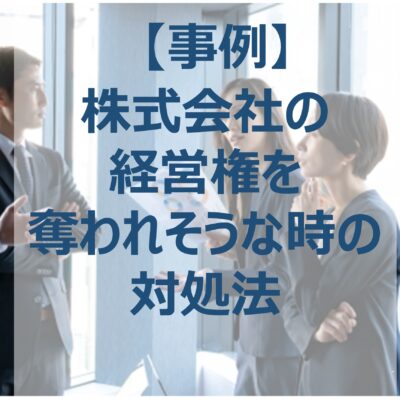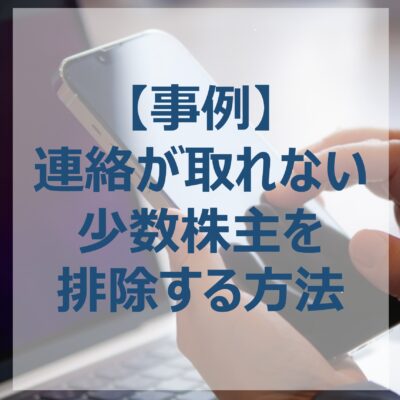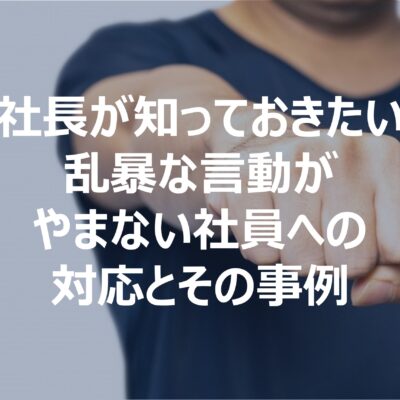「せっかく経験者を雇ったのに期待外れだった」「あんなこともできないなんて、経歴詐称だ」。 中途採用の場合、企業は一定の能力があることを期待して経験者を採用しています。ところが、経歴を見込んで中途採用したものの即戦力にならず、解雇を検討せざるを得ないという相談を受けることがよくあります。能力不足を理由に解雇する場合、雇用を継続できないほどの能力不足を証明するためには、どのようなことに注意が必要でしょうか。
1 中途採用の解雇
社員の能力不足を理由に解雇する場合、新人採用と中途採用では差があります。新人採用はノウハウやスキルがない状態で雇用し、会社が育てることを前提としているのに対し、中途採用の場合は職歴や実績に着目して採用することから、ノウハウやスキルがあることを条件に雇用するケースがほとんどです。 そのため、中途採用の場合、新人に必要とされるほど指導のプロセスを踏まなくても、能力不足を理由とする解雇が認められやすいといえるでしょう。しかしながら、解雇である以上、ハードルが高いことに変わりはありません。では、中途採用者を解雇する場合に、何に注意して行動しなければいけないか、順を追って確認していきましょう。
2 採用時の注意点
(1)経験者採用に注意
中途採用をする時、こんなやりとりをしていませんか。「前職はあの会社で勤めていたのですか。それは心強い」「この業界でもう15年の経験があるんですね」。
このように、相手の経験や経歴に着目し、能力を見込んで採用する場合があります。しかしこれは、単に経験者を採用しただけで、能力に基づいて採用したことにはなりません。なぜなら、「前職はあの会社」「業界でもう15年」こういうやりとりをしながら、会社はある一定の能力があることをイメージしているはずですが、それは会社の一方的な期待に過ぎないからです。これでは特別な業務能力を持つことを前提とした採用とはいえません。
(2)求める能力の明確化
一定の能力があることを前提に中途採用するのなら、どのような能力がどの程度必要なのか、何ができることを求めるのか、採用時に条件を明確にする必要があります。
「経験者募集」や「良い人がいれば採用」というなんとなくのイメージでは、能力採用になりません。たとえ期待外れがあったとしても、求める能力を明確化したうえで採用していない以上、その社員を能力不足で解雇することは難しくなります。
(3)目標の見える化
求める能力を明確にしたら、それを採用時に応募者に示しておかなければいけません。そうしないと、会社がその能力を見込んで採用したことにはなりませんし、雇われる側も、その能力があることを前提に雇われたという合意があることにならないからです。具体的には、求人広告、面接時の確認事項、雇用契約書(資格や待遇の記載)が証拠となるので、これらに明記する必要があります。
例えば、営業職であれば、営業にあたる可能性のある相手先のリストを見せつつ、どのくらいの期間でどれだけの数値目標があるのかを示すのも一つの方法です。具体的な仕事内容のイメージや、数値目標をあらかじめ示しておくことは、ミスマッチを防ぐ上でも非常に重要になります。また、一定の資格保有を条件とすることもあります。
裁判例の中には、応募者に営業方法のプレゼンをさせていたことが会社に有利に判断されたものもあります。裁判所は採用の過程を踏まえ、応募者に求めた条件は単なる期待にとどまらず、雇用契約の一内容となっていたものと理解できるとしました。その上で、プレゼンで自らリストに上げていた見込み顧客に対しても営業活動を行わなかったことが、能力不足と認める材料となり、解雇は正当であると判断されました。
(4)経歴の確認
中途採用の能力不足社員の場合、同時に経歴詐称が発覚することがあります。このようなことは、できれば採用時に防ぎたいものです。経歴詐称と言えるには、社員自らが履歴書に記載した経歴と実際の経歴が異なっていなければなりません。そのため、履歴書に職務経歴を書かせることは必須です。同時に経歴を客観的に確認するための方法として、年金記録の照会があります。年金事務所で年金記録を本人に取得させると、そこにこれまで、どこの会社で何年間、厚生年金に加入していたかを確認することができます。
(5)待遇の明確化
能力を前提としての中途採用のつもりでも、入社後の待遇が平均的な社員と変わらなければ、証拠の面で不利になる場合があります。
一定のポストにつけて職能手当を与える、専門職分野に配置して高額な給与を支払うなど、待遇面での厚遇がなければ、それだけの待遇を与えるほど高い能力があることを前提とした採用とは言えなくなるからです。
3 採用後の処遇
(1)試用期間の設定
試用期間とは、面接だけで適性を判断するのは難しいことから、採用後の一定期間、企業側が面接で見抜けなかった人材の適性を見極めるために設けられているもので、通常1カ月~6カ月を設定しています。いくら即戦力となることを期待した能力採用といえども、試用期間は設けるべきでしょう。なぜなら、外から来た人間が高いポストにつくことになるため、既存の社員と馴染めず、業務が円滑に進まない可能性もあるので、適性を見極めるのが重要だからです。また、試用期間内に一定の評価ができなければ、本採用しないと、試用期間の意義を伝えておくと、雇われる側も覚悟をするので、能力不足が発覚した場合に退職までの流れがスムーズになります。
(2)予定されていた業務に従事
一定分野での能力を見込んで採用した以上、採用時に予定していた業務に従事させなければなりません。もし、別分野に従事させ、「能力が足りない」と思ったとしても、その分野ではいわば新人と同等になるため、能力不足を理由に解雇はできません。
(3)能力不足の証拠
能力不足で解雇するためには、前提としていた能力がなく、雇用を継続できないという証拠が必要になりますが、どのような証拠が必要かは、職種によっても異なります。
業務上のスキル(システム開発や介護、医療業務など)が明確なものについては、実際にテストを実施し、その結果が証拠になった例もあります。接客や営業職では、個人の売上成績、顧客への訪問や連絡の頻度、クレームの記録や指導録などが証拠として認められます。
4 退職のタイミング
(1)試用期間終了のタイミング
試用期間とは、読んで字のごとく「お試し期間」であるから、試用期間中は自由に解雇できる、と思う方もいるかもしれません。しかし、それは誤った認識です。
むしろ試用期間中は基本的に解雇できません。いわばテスト時間内に強制終了させるような行為で、能力の有無を見極めずに解雇したということになり、解雇が無効になってしまいます。従って、雇用を継続するかどうかは試用期間の満了時に判断しなければなりません。
(2)退職勧奨
会社側は、解雇を言い渡すよりも先に、中途採用の社員自ら辞めるつもりはないのか、退職勧奨を行う必要があります。解雇は会社が一方的に辞めさせるものなので、解雇された社員が不満を抱いて訴訟を起こすなど、紛争のリスクがあるため、慎重に対応しなければならないからです。
退職勧奨をする場合でも、会社が能力不足だと判断した資料(証拠)を示すことが有効になります。きちんと根拠を示すことにより、社員の納得(諦め)も付きやすいと言えます。
退職勧奨のタイミングは、試用期間満了前に行ってください。試用期間を過ぎてしまうと、本採用になり、その時点で「雇用を継続できない」と判断していないのに、その後に能力不足で退職させるのはハードルが上がってしまうからです。
また、会社側は能力不足を察知した時点で、定期的に面談を実施し、指導や原状の評価を伝えなければなりません。それを行わず、試用期間満了日にいきなり退職を勧めても、受け入れられませんので、ご注意ください。
(3)解雇
能力不足で解雇する場合は、特別な能力を見込んで採用した証拠とその能力に満たないことが判明した証拠、二つの証拠を揃える必要があります。これがなければ、解雇は無効になってしまいます。
特別な能力を前提とする中途採用の場合、雇われた社員としても一定の自負があり、プライドを持っている場合が多く、解雇した場合「不当解雇である」と訴訟などの紛争に発展しやすい人ともいえるため、会社が解雇に踏み切るには、きちんとした証拠を揃える必要があります。
5 まとめ
多くの企業において、中途採用者には即戦力や特別な能力を見込んで採用しています。しかし一方で、期待していた能力がなく、能力不足で解雇しようとするとき、どのような能力を前提に採用したのかという証拠も、その能力が不足しているという証拠もきちんと揃っていないケースが多く見受けられます。
経験豊富な中途採用社員に対して、採用側はどうしても期待してしまいますが、特別な能力を持つことを前提とした雇用契約になっているか、今一度確認するとともに、採用する時点から「もし期待外れだったら」ということを念頭に対策をする必要があるでしょう。