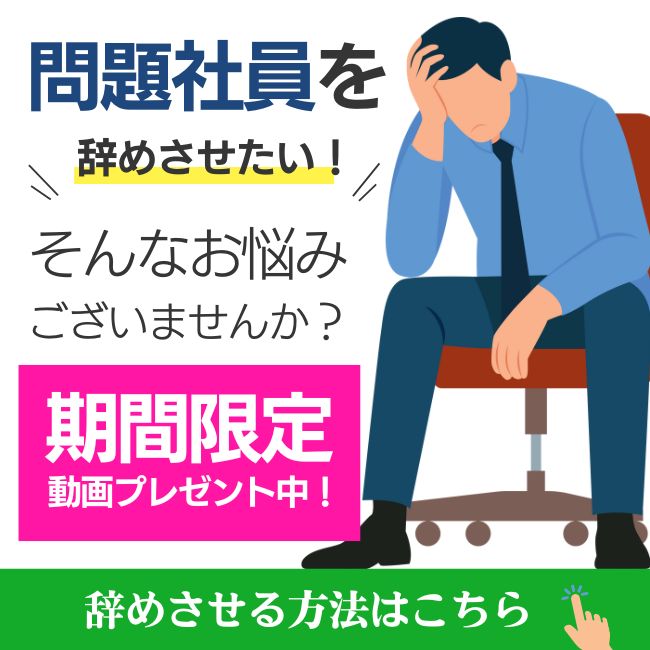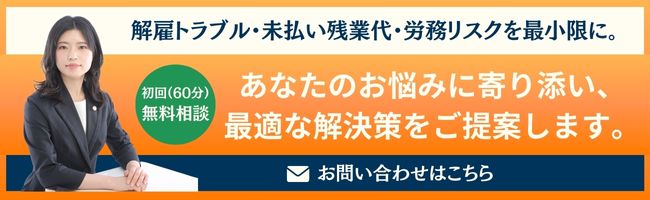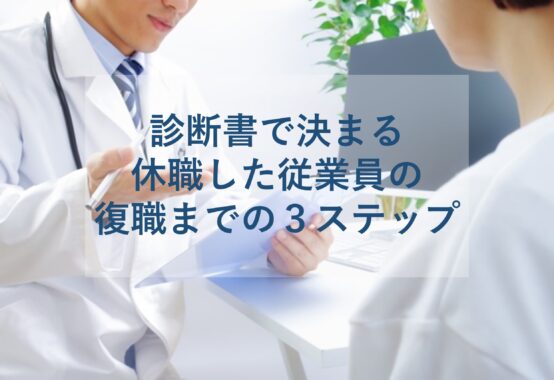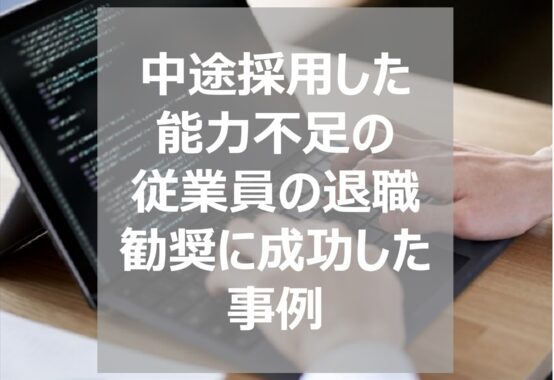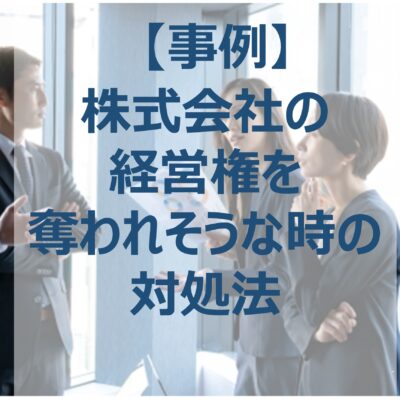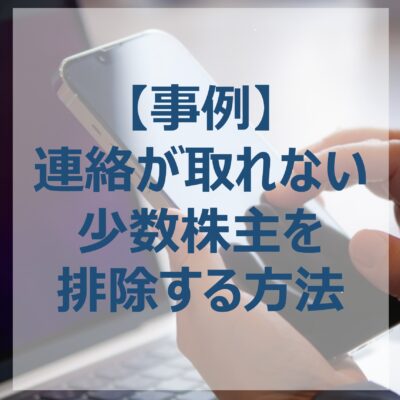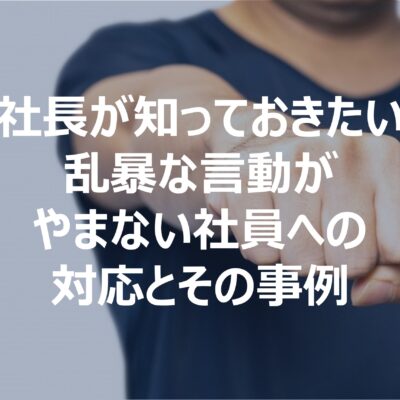生産性を重視する会社にとって、仕事の能力が低い社員は、頭の痛い存在です。たとえ会社のお荷物になっていたとしても、能力選考をした中途採用でないかぎり、易々と解雇することはできません。今回は能力不足の社員への対応方法をご紹介します。
1 能力不足と解雇の関係
経営者から「仕事ができない社員を解雇したい」と相談を受けることがあります。このような社員であったとしても、すぐに解雇をするとほぼ100%無効になります。なぜかというと、会社には「解雇回避義務」があるからです。
解雇をするには、(1)解雇に客観的合理的なに理由があり、(2)社会的相当性がないといけません。能力不足の解雇の場合、かんたんにはこの2つの要件を満たしません。なぜなら、社員を教育して仕事ができるように指導するのが会社の務めだと考えられているからです。能力不足の社員は、解雇するのではなく、できるようになるまで会社が指導しなければならないのです。そのような努力を会社が尽くしたのに、それでもなお、普通に働かせるには能力が欠けるといえてはじめて、解雇が可能になるのです。解雇は最後の手段といわれているのはそのためです。
2 能力の評価
能力不足の社員に対処する場合、どのような対処をするにしても、その社員の能力を評価する必要があります。
どんな能力がどの程度足りないのか、客観的に明らかになっていなければ、どのような対処が必要かも明確にならないからです。
評価といっても、どのようなことをするのか、漠然とするでしょう。必要なのは、何ができないのか、求めているレベルはどういうものなのか、そこから比べてどの程度レベルが不足しているのかが分かることです。社内に人事評価の基準があればそれを使えばいいのですが、ない場合でも、先ほどの3点を意識して、日々の業務指導を書面に残したり、定期的な評価面談を行い記録することが有用です。
なお、相対評価に基づいて社員に不利益を課すのはいけません。なぜなら相対評価である以上、必ず下位の社員がうまれてしまうからです。相対評価で下位の社員が、必ずしも絶対評価(その会社で求められる能力の基準)で劣るとは限らないからです。相対評価で下位であることだけではなく、絶対評価の視点で、会社で求められている能力に足りているのかを判断しなければいけません。
3 改善指導
社員にどんな能力がどの程度不足しているのか把握したら、まずはそれを改善できるように会社が指導や教育をする必要があります。なぜなら、社員を育てるのは会社の務めだと考えられているからです。会社が指導を尽くしてもなお、初歩的なミスを繰り返したり、基本的な業務を一人で満足にこなせないという状況になってはじめて、解雇を検討することができるようになります。
そういう意味で、改善指導は、解雇の前段階のステップでもあります。解雇の前提となる重要なステップですから、いつ、どのような指導を与えたのか、その後に改善が見られたのかは、きちんと指導録などのかたちで記録に残しましょう。また、指導の過程で社員にミスが見られる場合には、始末書を取ったり、懲戒を検討しましょう。
会社が指導・教育を行う際に書面や記録を作成することは、指導内容が具体的・客観的になることに加え、後に解雇などをめぐって紛争に発展した場合にも、会社が能力不足を立証するための重要な証拠となります。
4 待遇の変更
会社の就業規則や賃金規程に降格や減給など、能力に応じて待遇を降下させる制度がある場合には、活用しましょう。これは、解雇を検討している場合には、必ず解雇の前段階で実施した方がよいでしょう。なぜなら、社員からすると、解雇されることに比べれば、待遇が悪くなっても雇用が継続される方がマシだからです。
いくら待遇を下げる手段があったとしても、形式的にあてはまるかどうかだけでなく、その社員の待遇を下げなければ見合わないほど能力が低いのかどうか実質的に検討しましょう。この時、前例や他の社員の待遇レベルなどが参考になるでしょう。
また、会社に他の部署や他の種類の業務があるならば、問題の社員の希望を聞きつつ、配置転換を行うことも、検討してください。なぜなら、会社が様々な業務への適性を図り、それにも関わらず満足に任せられる業務がなかったということが、解雇を有利にするからです。逆にいうと、配置転換できる業務があるにもかかわらず、配置転換をせずに解雇をすると、解雇が無効になりやすくなります。
5 十分な面談
改善指導をする時も、待遇を下げる時も、能力の低い社員に対して何らかの措置を取ろうとするなら、それまでの間に十分なほど面談を繰り返し、会社がその社員の能力の低さを問題視していること、能力が低いと評価している理由を本人にきちんと説明するようにしましょう。
例えば、会社が求めた事項に対して、実績としてどうだったのか、具体的な事実を、時系列で、客観的な記録・数値(営業成績やミスの回数など)によって、整理することが必要です。
社員は能力不足を理由に、何かしら不利益な思いをする訳ですから、いきなり不利益な対応を受けると、当然、社員は会社に対立的な感情を抱きます。少しでも理解や納得を得るよう、会社としても丁寧な説明が必要です。
6 懲戒歴の有無
能力不足で解雇を検討するとき、その社員に懲戒歴があるかどうか、その時期や内容を確認しましょう。能力不足に加えて、過去複数の懲戒歴があったり、近年の懲戒歴がある場合には、社員としての適正性を判断するうえで、考慮できる場合があります。特に、能力不足の内容と関わりのあるような懲戒歴である場合は有効です。例えば、能力不足の内容が、日頃の注意散漫な勤務態度だったとしましょう。その社員が以前に注意不足でミスを犯し、懲戒されていた場合は、その社員が以前から同じ問題を抱えているといえます。逆に、懲戒歴があると言っても5、6年も前のものだったり、勤務態度や能力不足と関係のない理由での懲戒の場合には、懲戒歴があることを重視して解雇を正当化させることはできません。
7 能力不足による解雇
指導をしても改善が見られず、雇用を継続するには不適切といえるほど社員としての能力が劣る場合には、最終手段として解雇を検討します。参考までに、能力不足による解雇の裁判例をご紹介しましょう。
<解雇を否定した判例>
裁判例1〜セガ・エンタープライゼス事件(東京地裁判決平成11年10月15日)
労働者XはY社に就職し、複数の部署での業務を経験したが、どの部署でも問題を起こして上司に注意されることや、顧客から苦情がなされることがしばしばあった。年3回実施される人事考課で、Xは相対評価により下位10パーセントであり、YはXを解雇した。しかし、判決で解雇は無効と判断された。その理由は、解雇するためには、平均的な水準に達していないというだけでは不十分であり、著しく労働能力が劣り、しかも向上の見込みがないときでなければならず、……解雇事由を常に相対的に考課順位の低い者の解雇を許容するものと解することはできない。YはXに対し、更に体系的な教育、指導を実施することでその労働能力を向上する余地もあったといえると判断された。
<解雇を認めた判例>
裁判例2~前原鎔断事件(大阪地裁判決令和2年3月3日)
労働者Xは新入社員でも3か月で習得できる作業もこなせない上、注意や指導を受けても、作業中の事故や怪我が絶えないことから、Y社は能力不足を理由にXを解雇した。
判決では、Xは、……複数回の始末書や顛末書の提出、出勤停止を含む3回の懲戒処分、さらには度重なる注意指導を受けており、これにより、「就業状況が著しく不良で就業に適さないあるいはこれに準ずるもの」にあたることは明白として、解雇を有効と認めた。
裁判例3~東京高裁判決平成27年4月16日~
労働者Xについて、業務過誤及び事務遅滞を長年継続して引き起こしており、繰り返し必要な指導をしたが改善されなかったとして、能力不足を理由にY社がXを解雇した事例。
判決では、Xは、上司の度重なる指導にもかかわらずその勤務姿勢は改善されず、かえって、Xの起こした過誤、事務遅滞のため、上司や他の職員のサポートが必要となり、Y全体の事務に相当の支障を及ぼす結果となっていた。Yは、本件解雇に至るまで、Xに繰り返し必要な指導をし、また、配置換えを行うなど、Xの雇用を継続させるための努力も尽くしたものとみることができ、Yが15名ほどの職員しか有しない小規模事業所であり、そのなかで公法人として期待された役割を果たす必要があるとして、解雇を有効と認める。
7 まとめ
能力の低い社員への対応は、能力改善のために指導を尽くすことが基本になります。ただ、丁寧に優しく指導をするだけではなく、改善が見られなかった場合にどうするかを想定しながら対応することが求められます。こうした指導は、一回で効果が現れるものではなく、状況に応じて繰り返すことが必要であることも少なくありません。一歩一歩を間違えないよう注意深く対応しましょう。