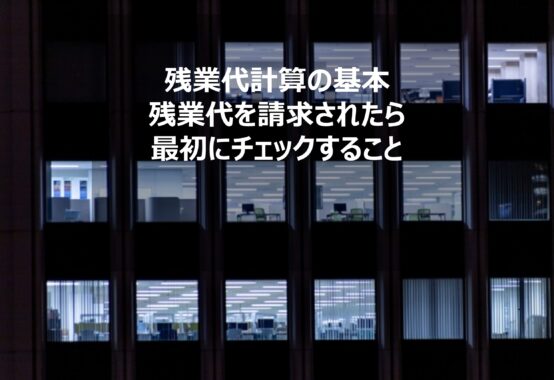未払い残業代の請求は、もうすでに辞めた従業員か、辞める直前の従業員からされることがほとんどです。請求を受けた段階で、数年分の未払い残業代が溜まっている状態なので、百万円単位の高額請求になることも珍しくありません。この請求に対し、いかに支払いを抑えるか、会社がすべき反論方法についてご紹介します。
1 タイムカードと実態
(1)タイムカードの位置付け
残業代は、実際に働いた時間に基づき計算されます。そのため、未払い残業代の請求も、実労働時間を元に計算します。多くの場合、タイムカードなどの出退勤記録をもとに残業代の計算を行いますが、なかにはタイムカードでの出退勤管理をしていなかったり、タイムカードはあっても実際の勤務とは乖離がある場合があります。
実際の勤務と乖離がある、とは、例えば、早く出勤しても、決まった時間まではタイムカードで出勤を打刻しないことになっていたり、逆に、仕事と関係ないことをして残っているのに退勤の打刻をしていない場合です。タイムカードが実際の労働時間の管理に役立たない場合、どうなるのでしょう。
労働時間の管理は、会社の責任です。そのため、タイムカードがなく、労働時間の管理が行われていなかった場合、会社の言い分は認められにくくなり、社員が主張する労働時間の言い分がとおりやすくなります。また、タイムカードがあっても、実際の労働時間とは違う場合、いわば、労働時間の管理が不徹底だった場合には、客観的な記録であるタイムカードどおりの労働時間であったと扱われてしまいます。
(2)タイムカードに基づかない請求
最初に従業員から未払い残業代の請求が来る時、従業員の手元に必ずしもタイムカードがあるわけではありません。従業員はいつもの勤務時間の習慣や自分の記憶、スケジュール帳などに基づいて、大体で残業代を計算してきている場合もあります。
残業代を請求された会社としては、必ずしも従業員の請求が正確な訳ではないということを踏まえて対応する必要があります。タイムカードやシフト表などと見比べながら、勤務時間を削り、残業代を減額する要素はないかを探りましょう。
(3)タイムカードと異なる実態
もし、タイムカードが正確な労働時間を反映したものではなく、「本当の労働時間はこうなんだ」という言い分がある時は、タイムカード以外の方法で、それを証明しないといけません。これはかなり難しいことです。一例をあげますと、パソコンのログの時刻、カメラの映像、出入口の施錠解錠時刻やゲートの通過時間、交通ICカードの記録、日報で報告された業務時間などが有用です。しかし、こういったものが入手できる場合は、限られてしまいます。
過去の裁判例や事案では、勤務時間中に自身の開業準備をしていた場合、完全自由参加の研修に参加していた場合、毎日決まって喫煙休憩を取っていた場合、泊まり込み勤務で職場に布団やシャンプーがあり、仮眠や休憩が確保されていた場合などに、労働時間が従業員の言い分よりも少ないと認められたことがあります。
業務と関係のないことをしていたり、自由参加で人事考課上も考慮されない行事に参加している時間は、労働時間と認められません。また、休憩時間が確保されていると、その分労働時間は減るので、残業代の圧縮に繋がります。ただし、要注意なのは、従業員がこれらのことをしていたと証明するのは、難しいということです。会社も逐一、従業員の行動を監視しているわけでも、それがきちんと証拠として残っているわけでもありません。たまたま証拠があったりした幸運な例だけで、会社が残業代請求に勝てたともいえます。逆にいうと、日頃から従業員の勤務中の行動に無駄を感じる場合は、きちんと禁止して止めさせる他、注意して日時の記録を付けたり、労働時間管理や給与計算の時に残業時間から除外するようにしましょう。いずれにしても、勤務の実態について、いかに説得力を持たせて反論できるかが大切です。同じ仕事をしている従業員のなかでも一人だけ残業が多かったりする場合、他の従業員のタイムカードや証言も資料にしつつ、本当に業務をするために残っていたのか、ということを追求し、減額する余地を探ります。
2 残業の禁止・許可制
会社が従業員に残業を禁止していたことを理由に、残業代請求で勝てる場合があります。例えば、残業を禁止し、仮に勤務時間を過ぎても残務が生じた際は、上司に引き継ぐように指導していた場合、従業員がそれを無視して残業しても、残業代の請求を認めなかった裁判例があります(東京地裁平成15年12月9日判決)。会社が残業を禁止する命令を出しているのに、これに反して残業をするのは、会社の指示によるものではなく、残業代の請求は認められない、と判断されました。
ただし、残業を禁止したり、残業を許可制にしたりする場合、かたちばかりのものではいけません。結局、残業を黙認している場合や、残業をしないと終えられないような業務量を与えていた場合には、残業代の請求は認められてしまいます。
従業員の中には、こだわりが強く、自分が納得できるまで時間をかけて業務を遂行しようとする人もいます。会社はそれに気づいて不満に感じているのであれば、きちんと業務命令を出して禁止をしないと、結局は労働時間が認められて、残業代が発生することになってしまいます。
3 管理監督者
従業員が管理監督者である場合は、残業をしても残業代は発生しません。ただし、この管理監督者とは、単に役職などの肩書がついていたり、会社の組織体制のなかで管理職に区分されているだけで認められるわけではありません。
管理監督者とは、経営者と同様に労働条件の決定や労務管理を行う人のことです。経営者と同じ立場で仕事をしており、その重要性や特殊性から、労働時間等の制限を受けません。一般的には部長以上や工場長以上の人を指しますが、あくまで名称ではなく、実体の責任や役割に沿って判断します。
これまで管理監督者と認められた例は、証券会社で支店を統括していた支店長、タクシー会社で最高額の給与をもらいながら多数の乗務員を指導していた営業次長などがあります。
一方で支店の運営に広く関わっている人でも、人事の権限がなかったり、その人自身がタイムカードなどで労働時間を管理され、出退勤の時間の自由がなかったりすると、管理監督者とは認められにくくなります。
4 消滅時効
残業代請求には、消滅時効があります。消滅時効とは、一定期間、請求しないでいると、その権利が消えてしまって、請求ができなくなるというものです。残業代の請求権の時効は3年です。ただし、時期は未定ですが、将来的には時効は5年まで延びます。
従業員から残業代を請求された場合、3年以上前の給料日のものは、消滅時効にかかっているので、それを指摘すれば、払う必要はなくなります。どこまで遡った残業代を請求されているのかもチェックしましょう。
5 まとめ
残業代請求をされた際、それが過大な請求であるときは、適切に反論する必要があります。一日一日に計算の誤りがないか、地道にチェックし、勤務の実態についていかに証拠を揃えて主張できるかが、減額のポイントになります。
一度、未払い残業代の請求をされた会社は、日々の業務で新たな残業代の未払いを生んでいるということでもあります。
このような苦労をする前に、または一度でもしたら、日々の労働時間管理の見直しをはかりましょう。