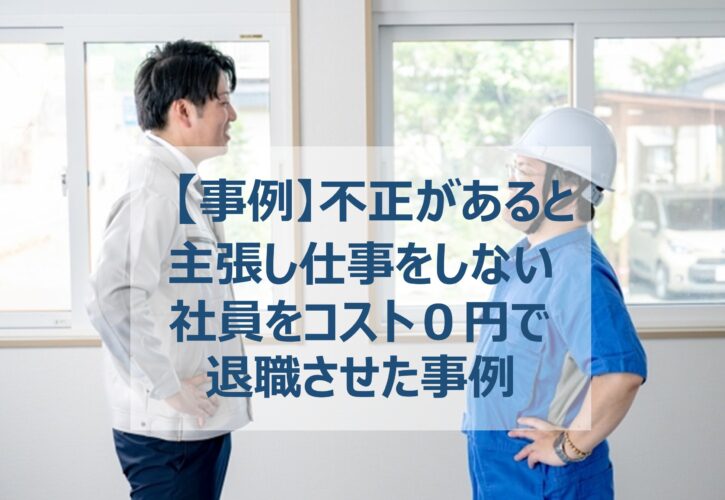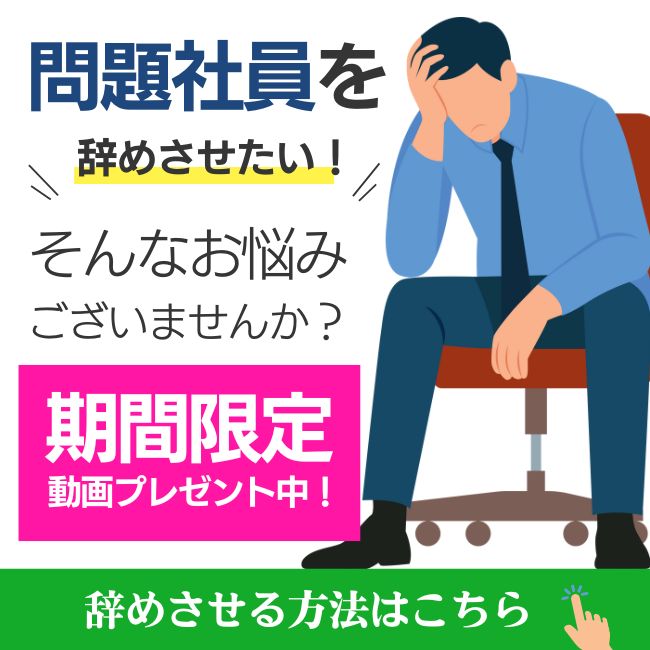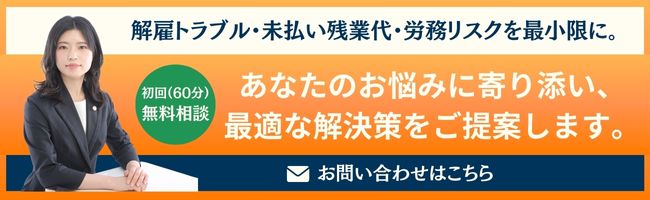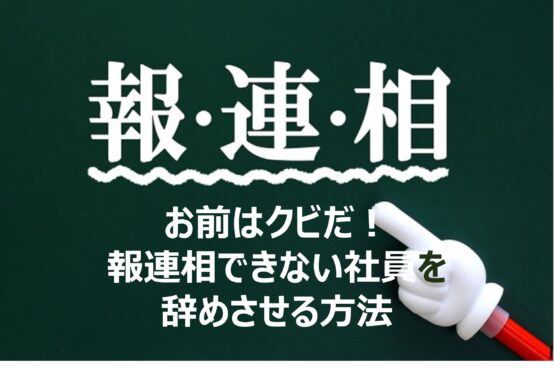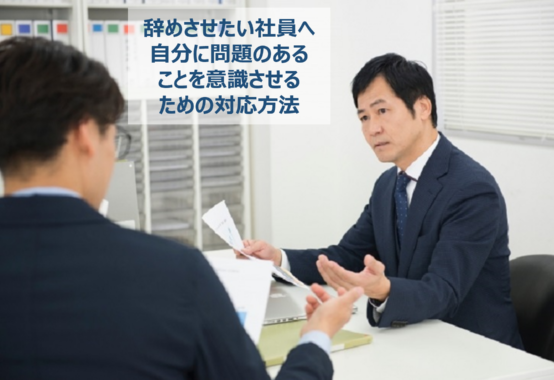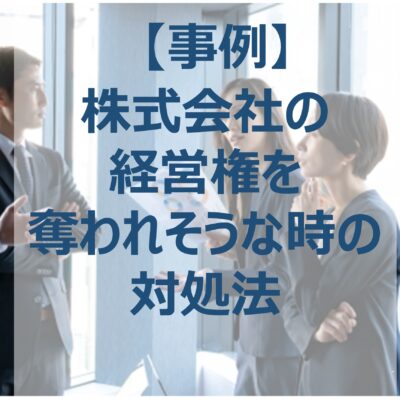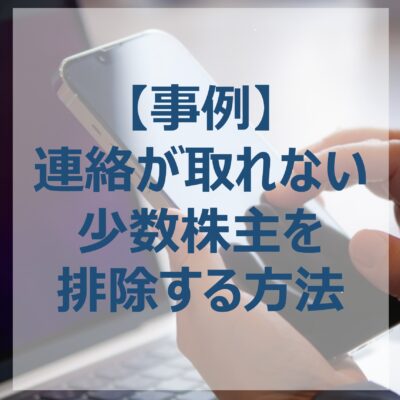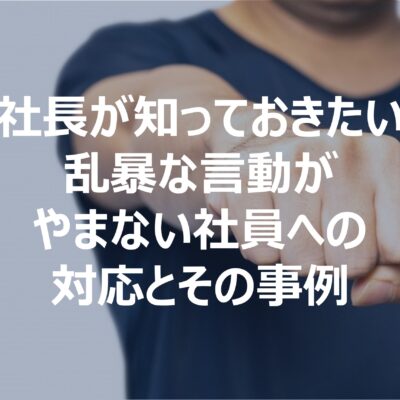ある日社員が突如、会社の不正を主張して、仕事を拒否する、このような事態に直面した際、どのように対応すればいいでしょう。実は、このような事例は珍しくはありません。社員は正義感からか、あるいは、日頃会社に鬱憤が溜まっていたからか、会社に落ち度がありそうなことを槍玉にあげて、職務を放棄することがあるのです。
1 不正を主張して仕事を拒否した社員
問題が発生したのは、業界大手企業の発注する現場に入る中堅の工事会社で、正社員20名程の会社です。社員が突然「この現場には不正がある」「不正な仕事には関わりたくない」と訴えて、出勤を拒否しました。社長は自身も現場経験を持つ創業社長で、現場のトラブルや社員の考えについては自分も精通しているとの思いから、トラブルの直後、その社員と直接連絡を取りました。ですが、社長が「現場に不正なんてない」と説明しても、その社員は聞き入れず、「会社が不正をしている」の一点張りで社長と押し問答になり、埒があかない状況になりました。
2 会社の不正を理由に職務放棄できるのか
社員が会社の不正を主張して、自分はその業務に関わりたくないと言い出した場合、その社員をその業務から外さなければいけないのでしょうか。
原則としては、答えはノーです。社員は会社の指示した業務を行う雇用契約上の義務がありますから、業務に不満があったり、不正があると主張していたとしても、業務を逃れられません。
ですが、例外的に、その業務から外さなければいけない場合があります。それは、本当に会社の業務に違法があった場合です。業務が違法であった場合には、直ちに会社はその状態を是正すべきですから、社員を違法業務に加担させるべきではありません。すぐに違法状態を正せない場合でも、少なくとも違法を主張している社員をその業務に就かせるべきではないでしょう。違法であると不満を募らせている社員を関わらせ続けても、違法を社外の監督機関やSNSに訴えるなど収拾がつかなくなる可能性があります。
違法な業務というのは、何も悪徳な業務やいかにも脱法的な業務だけではありません。資格や許可などが有効に及ぶ範囲を誤解し、業務にかかわる権限の範囲を超えてしまっていた場合も、無資格・無許可で業務をしているわけですから、違法な業務にあてはまります。また、社員が安全に働くために何をすべきかという安全配慮義務に違反していた場合も違法業務といえます。安全配慮義務というのは、その時、その状況によって、具体的に何をすべき義務があるのかが変化するものですから、違反する意図はなくとも、知らぬ間に業務上の危険を放置してしまい、結果的に安全配慮義務に違反した違法業務状態に陥っていることもあります。
3 初動対応
(1)ルールの確認
まず、本当に会社の業務に不正がないと言えるのかを確認しました。その社員が言うには、現場に特定の有資格者を置かなければならず、しかも、その有資格者は会社が自前で置かなければならず、同じ現場に入る他社の出した有資格者に乗っかるかたちではいけないというのです。ですが、本当にその業務を行う時にその有資格者の配置が必要になるのかどうか、また、必要だとしても他社の置いた有資格者ではいけないのかどうか、法的なルールや業界のマニュアルを確認しても、はっきりしませんでした。つまり、会社としては「うちの会社に不正はない」と根拠を持って主張できる状況ではありませんでした。
(2)目標の設定
社長の希望は現場に不正があると吹聴する社員をすぐにでも辞めさせることでした。
ですが、現場に不正があると社内で訴えるだけでは、解雇することはできません。解雇するためには、解雇に値するだけの理由(解雇の客観的合理的理由)が必要ですから、この程度の問題行動では解雇できないのです。
一方で、この時点で、その社員が不正があると言っている業務を行う現場に出ることを拒否しているのはわかっていましたから、この業務には配置しない方向性にしました。もちろん、一方的な仕事外しをしたと言われないよう、社員本人の意思確認もしなければいけません。
社員が不正を訴えている業務は、会社の中核的な業務で、その社員もその業務を扱う現場に出ることで歩合給を稼ぎ、収入の柱としていました。つまり、その業務から外してしまうと、社員としても会社としても、会社に在籍する意味がほとんどなくなってしまうのです。
会社としては、その社員の要求するとおり、やりたくない業務はやらせない、という対応を取ると、結局はその社員の待遇が下がってしまうという状況を実感させ、時間をかけて退職を決意させることを目標としました(退職しない場合には、不正を吹聴しないと誓約させたうえで業務復帰させるか、問題行動を起こした場合にさらなる待遇面での対処をする)。
(3)面談の実施
このように目標を決定したうえで、トラブル発生の初期段階で、社長、弁護士を交えて問題の社員と2回の面談を実施しました。面談ではまず、その社員の言い分を聞くというスタンスで臨み、社員の希望する現場をヒアリングしました。そのなかで、不正を行っていると主張している現場には出たくないと訴えたことから、会社としてもその現場に配置しないことには了承すると伝えました。それと同時に、その業務から外すとなると、配置できる現場が減り、歩合分の給与が減ることに合意できるかをその社員に確認しました。
実際、社員の希望に沿う現場は少なく、現場に配置できるのは、数回(1か月に1回くらいのペース)でした。ところが、その社員は現場が遠い、時間帯が早い、などと理由をつけて、結局出勤してくることはありませんでした。
また、当初の段階で、その社員は自身でも整理できていない不満や自分が正しいという思いを抱えていたので、弁護士とメールで複数回やりとりをすることにしました。メールのやりとりを通じて、その社員の抱える不満は、合理的に取り合ってもらえるほどのものではないことを実感してもらい、沈静化させていきました。
4 経過のフォロー
会社としては、不正を主張して出勤してこない社員であっても、社員として不公平のないように扱わなければいけません。定期健康診断を受けさせたり、現場資格維持のための年1回の法定研修も案内しました。結果的に、その社員は法定研修にも出てこなかったため、次年度4月以降は現場に配置することはできないこととなりました。
一方で、他の現場への配置を続けていましたが、実際には出勤してこないため、他の社員からは「あいつと同じ現場なら入りたくない」と不満も出るようになりました。
このような状況が続いて半年ほどで、もう一度、その社員と面談を実施しました。社員は自分が思っていたよりも現場に入れず不満だと漏らしていました。そこで、そうなった経緯をもう一度説明しました。その社員自身の希望で特定の現場から外していること、それ以外の現場は数が限られること、数少ない現場に配置してもその社員自身が配置に応じず出勤してこないこと、そのようにドタキャンされる状況では、会社としても配置できる現場がさらに限られてしまうということを順を追って説明しました。一つ一つの経過はまったくそのとおりな訳ですから、その社員も反発せずに説明を聞いていました。そこでこれからどうするのか、とその社員の意思を確認したところ、「まだこのままでいい」と答えたので、現状の対応を維持することにしました。
5 退職の合意
半年の面談後も同じような状況が続きました。会社からは1か月に1回ペースで仕事を配置し、その社員は配置要請に応じず出勤しないという状況が続きました。そのうち、年度が経過し、現場資格切れで一定の現場には配置したくても配置できない状況になりました。この時点で問題発生から1年近くが経過していました。
この段階で再度、その社員と面談し、これから会社でどうしていくのかと話したところ、「退職する」と答えたので、退職合意書をつくり、退職に至りました。
結局、退職させるために金銭を支払うということはなく、円満に合意退職に至ることができました。
6 まとめ
今回の事例は、不正がないと断言しにくい状況でしたので、問題の軸をずらし、その社員の要望どおりにするとその社員自身が困るのだということを実感させる対応を取りました。なお、今回の事例は、現場に配置させることで給与が変動する給与体系だったため、配置を絞ることが給与収入の減少に直結しました。もしも基本給が給与の大部分を占めるような場合であれば、出勤を絞っても給与の減少には直結しませんので、待遇面を切り下げるために別の対応を検討しなければいけなかったでしょう。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。