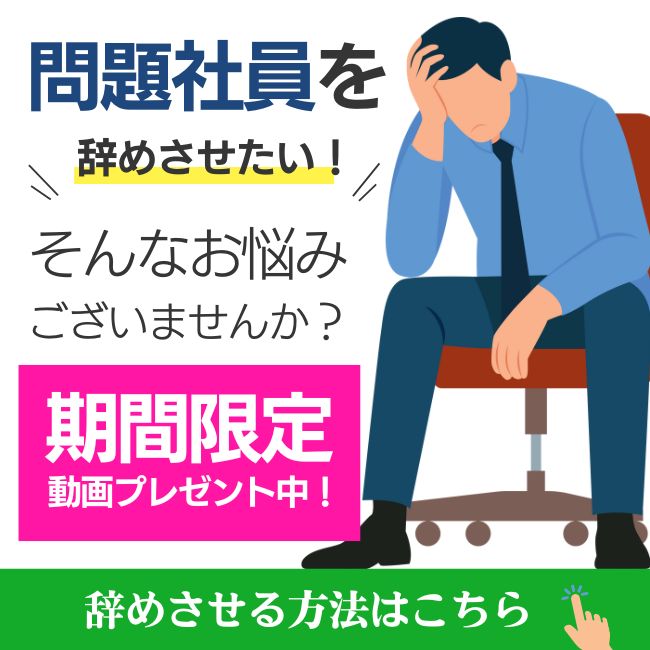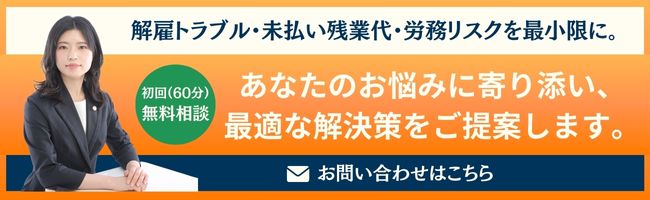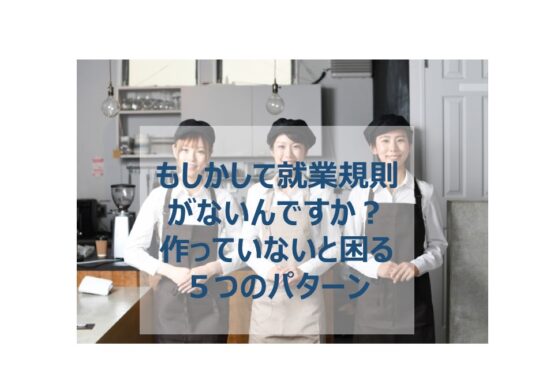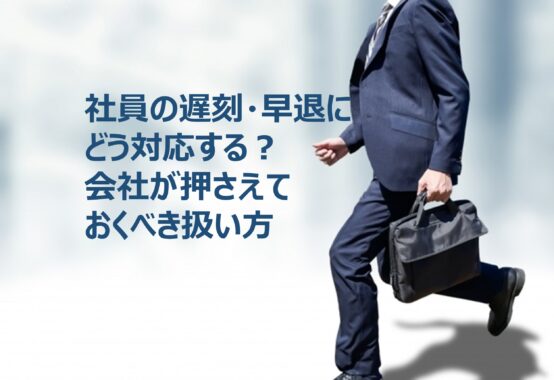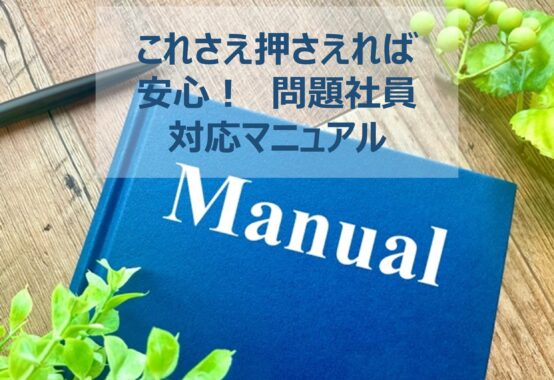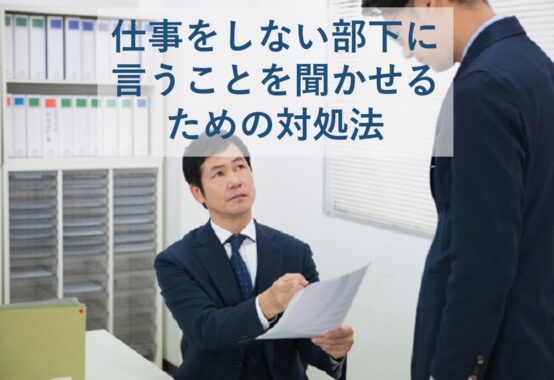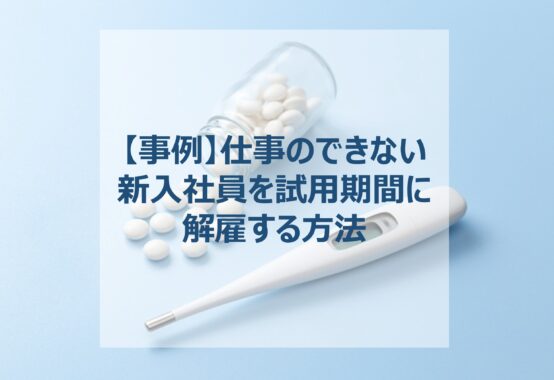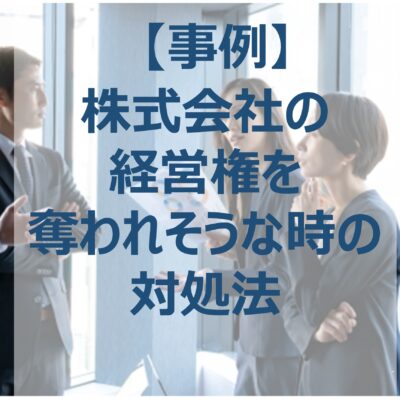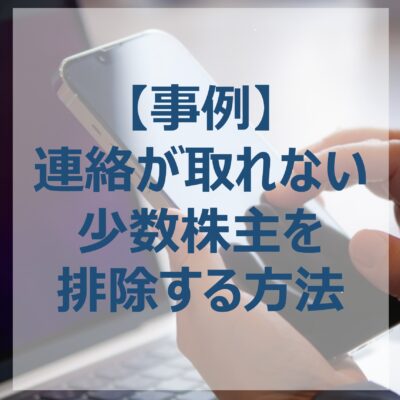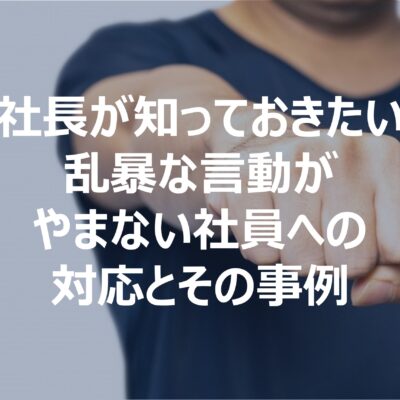普段仕事を行う際、従業員に対し、口頭での指導や指示をすることはあっても、書面で業務命令を発したことはない、という企業は少なくありません。「そもそも業務命令って?」「従業員が従わない場合どうなるのか?」といったところまで理解できている人は少ないでしょう。今回は業務命令とはどのようなものか、また、業務命令違反するとどうなるのかについて解説していきます。
1 業務命令とは
業務命令とは、業務遂行のために会社が従業員に対して出す指示や命令のことを指します。 従業員は会社の指揮命令のもとで働く存在なので、会社は従業員に対し、広範な業務命令の権限を持っています。ところが、時に従業員が会社の業務命令に正当な理由なく従わない場合があります。このような業務命令違反は、労働契約の基本を根本から覆すことになるため、その従業員には懲戒処分が下される可能性があります。懲戒処分という罰を与えるためにも、事前に従業員が「これはれっきとした会社からの命令で、破ってはいけないものなのだ」と自覚できるよう、業務命令は書面で渡すのが望ましいです。
2 業務命令が認められる範囲
(1)規律・人事
会社は従業員に対して広範な業務命令の権限を持っているので、日々の業務のやり方だけでなく、社内の規律を守るように業務命令を出すこともできますし、残業の命令や出張や転勤なども業務命令の一種といえます。
(2)安全・衛生
会社には社内の衛生を管理する権限もあるので、体調不良の従業員への受診命令や健康診断に行くように指示することも、業務命令として可能です。
(3)変わった業務命令
また、一見変わった業務命令であっても、業務としてやらせる理由があれば、認められる傾向にあります。例えば、協調性や仕事の効率性に問題があり、指導しても改善しない従業員に対して、一人で年賀状の宛名シールの貼り付け作業をさせた事案(東京地裁判決令和5年10月25日)でも、業務命令は適法でした。一見、仕事からのけ者にしているようですが、会社の年賀状なので、いずれにしても従業員の誰かが行う作業であること、その他の業務に難ありな従業員だったことも考慮されています。
3 ダメな業務命令の判断基準
(1)法律・就業規則違反
業務命令というのは、会社が適法な、正しい業務を行うために認められているものです。法律に違反するような業務(賄賂や不法投棄、情報漏洩など様々)や会社の就業規則や内規に違反するような業務を命じることはできません。たとえば、ハラスメント問題が解決されていないのに加害者と一緒に働かせるような業務命令や、健康上の問題がある従業員に対する残業命令なども、安全衛生に関する会社の法律上の義務や就業規則に反することになります。
会社の業務命令が違法だった場合、その違法な業務命令を拒否したとしても、その従業員を懲戒したり解雇したり、不利益に扱うことはできません。
(2)権利侵害
さきほど、健康診断や受診命令も業務命令として行えると解説しました。これは、社員を安全に働かせるために、必要な措置だからです。
その目的を超えた、個人のセンシティブな領域に踏み込むような業務命令は、社員の人格権を侵害するものとして違法になってしまいます。
例えば、業務上の必要がないのに、宗教を告白させたり、親族の情報などを提供させてはいけません。他にも、具体的に体調不良があって業務を軽減させる必要がある場合や他の従業員に感染する可能性がある場合は別ですが、基本的には病気や健康に関する情報はセンシティブ情報なので、提供を命令すると違法な業務命令になりやすいといえます。
(3)裁量権の逸脱・濫用
いくら会社に業務命令の権限が広くあるといっても、その権限(裁量)を超えたり(逸脱)、まちがった使い方をすると(濫用)、業務命令は違法になってしまいます。
どのような場合に業務命令の権限(裁量)に逸脱・濫用があるかというと、業務上の必要性がない、または少ないのに、不当な動機で、従業員に著しい不利益を与えるような業務命令をした場合です。
例を挙げると、労働組合に所属する従業員が、労働組合のマークを身に着けながら作業していたため、翌日、ほぼ丸一日、就業規則をすべて書き写すよう命令した事案では、明確な就業規則違反がないもしくは違反が軽微にもかかわらず、見せしめの目的で事務所に隔離して作業させたと判断され、裁量権を逸脱・濫用した違法な業務命令だと判断されました。
4 業務命令違反への対処法
(1)懲戒
会社には広く業務命令の権限がありますから、基本的には、会社の発した業務命令に客観的に違反する事態が生じれば、業務命令違反となります。
業務命令違反をとる際には、ダメな業務命令、つまり、違法な業務命令をしていないかを先ほどの判断基準にしたがって判断しましょう。業務命令違反が判明した場合には、見逃さず、懲戒処分をしましょう。
(2)懲戒の種類
懲戒は、就業規則に書かれているものを選択します。就業規則の懲戒事由にあてはまるかを検討してください。
違反した業務命令がどれほど重要なものだったか、何度目の違反なのか、ということを考慮しながら、基本的には軽い懲戒処分からスタートし、懲戒が重なるごとに徐々に処分を重くしていくのが順当でしょう。
(3)懲戒の手続
懲戒処分をする場合には、必ず弁明の機会を対象となる従業員に与えなければいけません。そこでの従業員の言い分を踏まえ、最終的な懲戒処分を決定します。なお、弁明の機会を与えさえすればいいので、従業員が拒否して欠席したり、「自分は悪くない」と否定することを言っても、会社の判断が拘束されるわけではありません。そして、懲戒を決定したら、処分通知書で本人に通知します。
(4)解雇
業務命令違反が繰り返されると、最終的に解雇も見えてきます。ですが、解雇というのは最後の手段で、条件がとても厳しいものです。
例えば、服装の乱れや数分の遅刻など、軽微な業務命令違反だけでは、業務違反が繰り返されたとしても、解雇は困難といえます。
業務命令を何度も繰り返し、どうしてそのような業務命令をしているのか目的をきちんと説明したにもかかわらず、従業員に改善が見られず、今後も改善が期待できない、その業務命令に従えないなら雇い続けることがふさわしくないといえる場合でないと解雇はできないと考えましょう。
5 まとめ
会社には広い業務命令の権限がありますが、かといって好きなように従業員を懲戒したり解雇できるわけではありません。円滑な業務遂行や会社の秩序を維持するためにも、業務命令をうまく活用して、従業員に規律を守らせるようにしましょう。