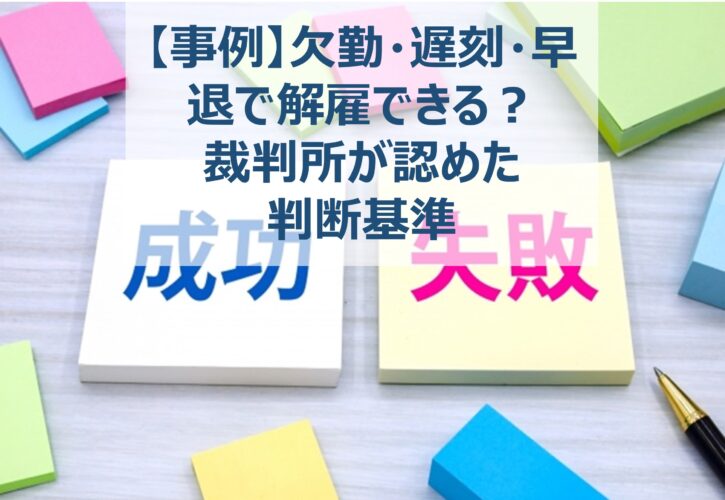欠勤や遅刻・早退を繰り返す従業員を解雇したい。経営者であれば、そのような感情を抱くのも無理はありません。しかし、たとえ頻繁に欠勤や遅刻・早退をしていたとしても、すぐに解雇してしまうのは失敗のもとです。なぜでしょうか? 解雇前のステップとして行うべき懲戒の処分と解雇の成功例・失敗例をご紹介します。
1 解雇と懲戒の関係
欠勤や遅刻・早退を繰り返す従業員がいても、直ちに解雇してしまうのは危険です。解雇を成功させるための条件は非常に厳しいからです。解雇を成功させるために、まず、解雇と懲戒の意味を整理しましょう。
懲戒とは、会社が従業員の不適切な行為を罰し、戒める処分のことです。懲戒には種類があり、軽いものから順に戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇となります。
次に、解雇とは、会社が一方的に従業員の雇用契約を終了させることです。解雇にはいくつかの分類方法があり、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇などの種類があります。
今回触れるのは、普通解雇と懲戒解雇です。
普通解雇にせよ懲戒解雇にせよ、解雇というのは労働者に対する最終手段です。そのため、問題のある従業員に対処する場合、普通解雇や懲戒解雇をする前に、より軽い懲戒(戒告、譴責、減給、出勤停止、降格)を試みることになります。
2 懲戒できる理由
欠勤や遅刻・早退で懲戒をしていいのか? そう思われるかもしれません。
欠勤、遅刻、早退で懲戒が認められる理由はなんでしょう。
欠勤や遅刻・早退は、雇用契約で約束された労働時間の一部を働かずに過ごしているのですから、債務不履行(民法改正で「契約不適合」と言い方が変わりました)にあたります。
働かない債務不履行があれば、直ちに懲戒をしていいのかというと、そうではありません。働かなかった分の給与を減額(欠勤控除)すればいいからです。
そうなると、懲戒をできるのは、欠勤控除にとどまらず、仕事に支障が生じた場合や企業秩序を乱した場合でなくてはなりません。例えば、仕事に支障が生じた場合とは、その人が遅刻したことで関係先に謝罪対応が必要になったとか、別の人が対応にあたることにより、他の業務が進められなかったというようなことです。また、企業秩序を乱した場合とは、無断欠勤を繰り返して社内のルールを無視し、そのことで他の社員の規律意識が低下するようなことを示します。
3 懲戒権の濫用に注意
懲戒解雇に限らず、懲戒の処分を実施する際には、懲戒権を濫用しないように注意しなければいけません。懲戒の客観的合理的理由がなく、懲戒をする社会的相当性がないと、その懲戒は懲戒権の濫用にあたり、無効になってしまいます。具体的には、次のような場合は、懲戒権の濫用とみなされます。
・懲戒の種類や該当する事由が就業規則に定められていない
・懲戒の規定が合理的でない(些細なことで懲戒できることにしている等)
・平等性がない
・違反の程度や内容に比べて下された処分が重すぎる(一発で即解雇する等)
・懲戒の手続が適正でない(弁明の機会を与えない等)
例えば、病気等の汲むべき理由があって欠勤しているのに無断欠勤と同様に懲戒したり(懲戒の規定が合理的でない)、これまで遅刻を見逃してきたのに、回数が溜まった時にいきなり懲戒したり(平等性がない)、一度も懲戒歴がない人を無断欠勤で即解雇したりすると(処分が重すぎる)、その懲戒処分や解雇は無効になってしまいます。窃盗を何度繰り返しても死刑にできないのと同様、遅刻を何度繰り返しても、本来は解雇できないのです。解雇が認められるのは、解雇せざるを得ない悪質性や悪影響がないといけません。
こう考えると、欠勤や遅刻・早退に対していきなり懲戒や解雇をするのではなく、段階を踏んで対処することの大切さがわかってくるでしょう。
4 懲戒のステップ
(1)欠勤・遅刻・早退の記録
欠勤・遅刻・早退をしたことを解雇の理由とするためには、その事実が証拠に残っていないといけません。普段、タイムカードの打刻や勤怠管理が適当だったりすると、欠勤・遅刻・早退の記録が残せなくなってしまうので、普段の勤怠管理を見直しましょう。
(2)指導の実施と記録
欠勤・遅刻・早退の記録を残せば、それだけでいいわけではありません。欠勤・遅刻・早退について、指導をしても直らなかったということを証拠に残した方がいいでしょう。そのために、きちんと指導を実施し、指導書を渡して控えを取ったり、誓約書を書かせたりしましょう。
(3)弁明の機会
懲戒手続には、懲戒を受ける側の従業員の弁明を聞く機会を設けることが必須です。これを行っていないと、いくら悪質な従業員であっても、懲戒は無効になってしまいます。
機会を与えさえすればいいので、たとえ従業員がその機会に応じなかったり、否定する弁明を行ったりしても、懲戒は実施できます。ただし、不意打ち的に事情聴取をしてはいけません。必ず従業員に、懲戒手続を行うことを見越して言い分を聞く場であることを伝えることが求められます。
(4)選択する懲戒の種類
懲戒には種類があり、軽いものから順に戒告、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇となります。懲戒は軽いものから実施するのが鉄則です。まずは懲戒する前に指導を行う、指導も聞かなければ戒告をし、それでも欠勤や遅刻・早退があれば、譴責、減給と段階をつけて徐々に処分を重くしていきます。
5 解雇の前段階
解雇をする前により軽い懲戒をした実績がないと、解雇が無効になってしまうことはよくあります。解雇の前段階で、必ず指導を行った上で、戒告・譴責や減給などの軽めの懲戒を実施しましょう。
6 【解雇の事例】成功と失敗
成功例
・事前の届出をせず、欠勤の理由や期間、居所を明らかにしないまま2週間欠勤した従業員に対する懲戒解雇を有効とした(開隆堂出版事件、東京地判平成12年10月27日)。
・6か月間に事前の届出なく遅刻24回、欠勤14日をした従業員について、事前届出のない遅刻・欠勤は、業務や職場秩序に混乱を生じさせるとして懲戒解雇を有効とした(東京プレス工業事件、横浜地判昭和57年2月25日)。
・区議会議員を兼務していた従業員について、公務のため、今後、所定労働日数の約4割の欠勤が見込まれることを理由とした普通解雇を有効とした(パソナ事件、東京地判平成25年10月11日)。
・4度の長期欠勤を含め傷病欠勤が多く、5年5か月の間に2年4か月に及び欠勤し、欠勤明けの就業にも消極的で、出勤時にも遅刻と離席が非常に多かったため就業規則上の解雇事由である「労働能率が甚だ低く、会社の事務能率上支障がある」にあてはまるとして普通解雇を認めた(東京海上火災保険事件、東京地判平成12年7月28日)。
失敗例
・3年にわたり恒常的に遅刻を繰り返していた従業員に対して、それまで何らの懲戒処分も行っていなかったことから、就業規則上の解雇事由である「その程度の著しく重いとき」に当てはまらないとして、懲戒解雇が無効になった(ヤマイチテクノス事件、大阪地判平成14年5月9日)。
・ラジオアナウンサーが2週間以内に2度の寝坊によりニュース放送ができなかったことを理由にした解雇について、寝坊自体は過失であり(故意ではない)、従業員がまだ勤続2年と勤続が浅く、一応の反省をしていたこと、1度目の寝坊は本来見逃されていたこと、会社が早朝放送の寝坊防止の措置を何もしていなかったこと等を理由に、解雇を無効にした(高知放送事件、最高裁昭和52年1月31日判決)。
・2か月間の無断欠勤を理由に懲戒解雇したことにつき、欠勤の発端が代表者からの暴力であり、使用者側に原因があるとして、懲戒事由に該当しないとした(紫苑タクシー事件、福岡高判昭和50年5月12日)。
・統合失調症により国内を転々としたり、イタリアに出掛けて行方不明となり、46日間の無断欠勤をした社員への懲戒解雇について、無断欠勤がそれまでの勤務状況・行動と連続性がないことから、無断欠勤がその社員の意思であることについて疑うべきであったとして、懲戒解雇を無効にした(国・気象衛星センター事件、大阪地判平成21年5月25日)。この例では、欠勤の理由について、会社がある程度の調査をすることが求められることがわかります。
7 まとめ
解雇を成功に導くには、その前段階である懲戒のステップが重要なカギとなります。
懲戒権の濫用に留意しつつ、欠勤・遅刻・早退の記録、指導の実施と記録、弁明の機会と適正に懲戒処分を行いましょう。解雇を成功させる条件は非常に厳しいだけに、「これだけ会社側は対応した」という実績の積み重ねがとても大切になってくるのです。