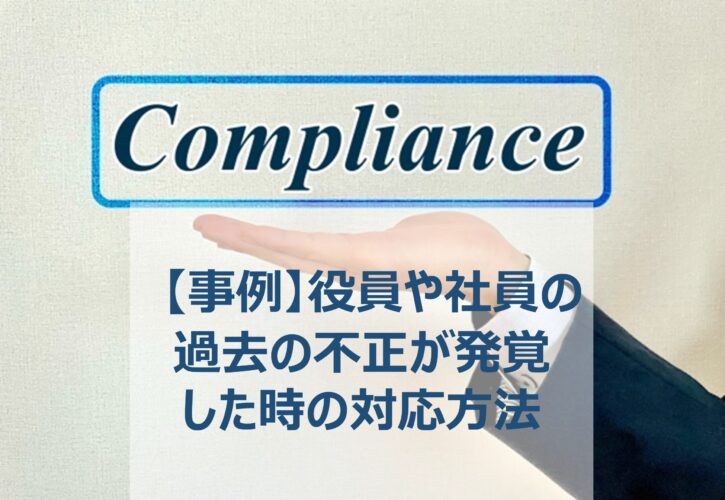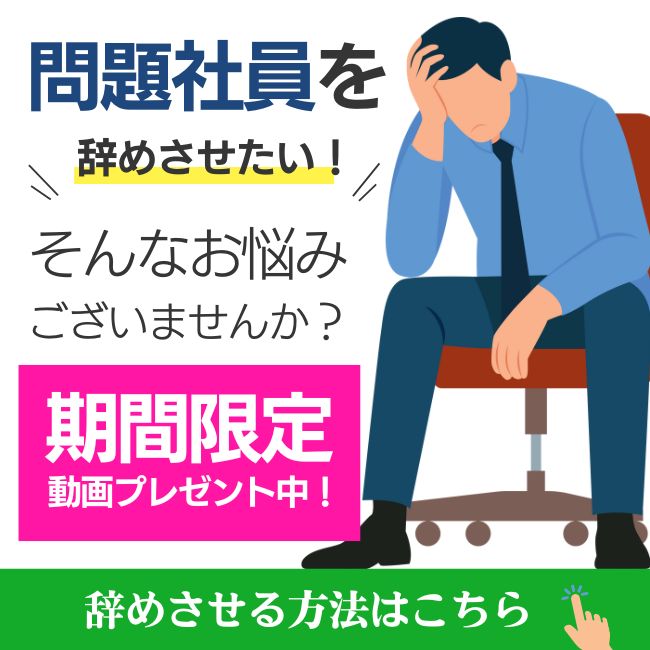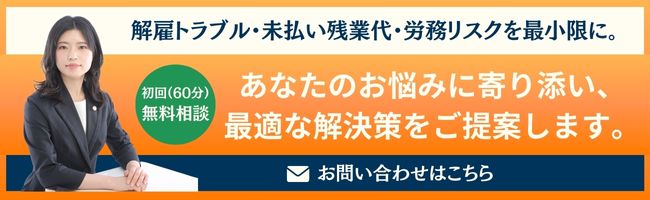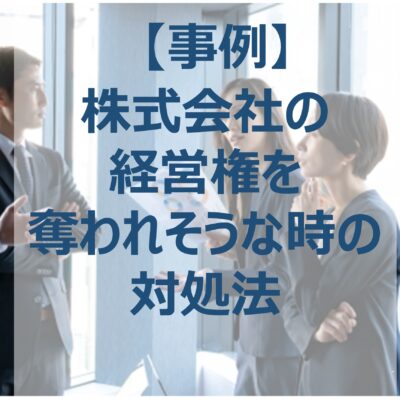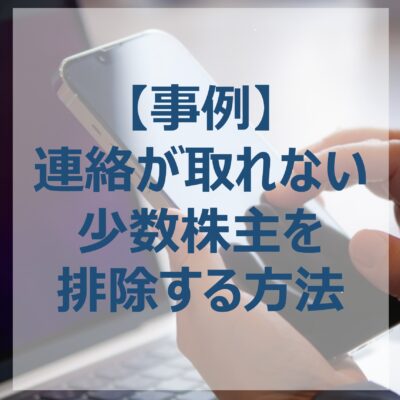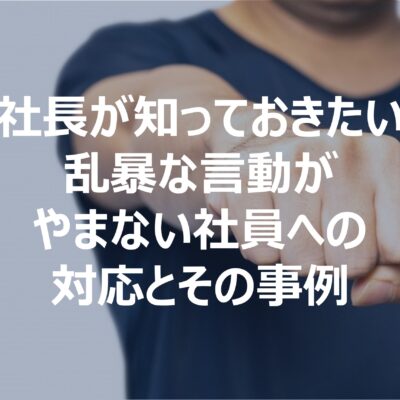好ましい話ではありませんが、社内で多少なりとも、ズルや不正を黙認している場合があります。ですが、それが問題化したり、正さなければいけないタイミングがやってきた時、会社としてどのように対処すべきでしょう。
1 所長の不正が発覚
ある建設会社の事例です。その建設会社は3つの事業所を抱えていて、その中でも本社から少し離れた事業所Aは、本社の目が常にあるわけでもなく、仕事の仕方や社員の雰囲気、勤務形態など、比較的緩やかで自由度の高い雰囲気がありました。
そのような風土のある事業所Aで、昔から本社には秘密裏に事業所の売上をプールしているという告発がされました。それは事業所Aで長年、所長を務めていたBが主導していたというのです。ただし、Bは既に定年退職しており、Bと同時期に事業所Aに配属されていた社員も不正に加担していたのかはっきりしません。
このように過去の不正が明るみに出た場合、会社はどのように対応すべきでしょう。
2 懲戒処分のルール
もし不正が本当に行われていた場合には、関わった社員に対して懲戒処分を行うかどうかを検討することになります。ここで、注意しておかなければならないのは、懲戒処分には5つのルールがあるということです。具体的には(1)懲戒処分の根拠規定の存在、(2)懲戒事由への該当、(3)相当性の原則、(4)公平性の原則、(5)適正手続です。
少し解説すると、(3)相当性の原則とは、不正行為の重さに見合った懲戒処分をしなければならないというものです。(4)公平性の原則は、同種同程度の事案に対しては同種同程度の懲戒処分をすべきというものです。
今回のように、過去から行われてきた不正を処分する場合、(4)公平性の原則への配慮が必要です。なぜなら、もしも過去、同様の不正が発覚したのに処分せずに済ませたのであれば、今回発覚した不正に対し厳しく懲戒処分を課すことは、この公平性の原則に反するからです。
3 二重処罰の禁止と一事不再理
過去からの不正に対処する場合、他にも注意しなければいけない原則が2つあります。それは、二重処罰の禁止の原則と一事不再理の原則です。この2つの原則は、法律のルールの中でも重大な原則ですので、例外なく、違反することは許されません。
二重処罰の禁止とは、同じ事実を理由として処罰ができるのは1回きりであり、同じ事実を理由として2回以上の処罰をすることは許されないというものです。もしも過去に既に不正が発覚していて、そのことで何らかの処分を受けているのであれば、もうそのことで新たな処分を下すことはできません。
一事不再理とは、一度認識されたり、調査されたりして処分を行うかどうか審理された事実については、後に再検討を加えて新たな処分を決定することはできないというものです。もし過去に不正の事実が会社に知れていて、それでも処分を下さずに放置した場合には、後から思い直して処分を下そうとすることは許されません。
このように、過去の不正が、時代や価値観の変化によってより重い処分をすべきだったということになったり、問題が取り沙汰されて再燃したとしても、すでに過去の時点で発覚していた不正に対しては、二重処罰の禁止や一事不再理によって新たな処分を加えることはできなくなります。
4 過去の悪い慣習の一掃
もし、過去からの不正の事実を会社が認識したり調査したりしつつ、何も処分を下さず放置していた場合には、一事不再理の原則から、今から処分を下すことはできません。そして、懲戒処分の公平性の原則からすると、今後、新たに同じような不正が行われたとしても、それに対しても懲戒処分を下すことが難しくなってしまいます。そうすると、会社は同じような不正に対しては未来永劫、目をつぶらなければならないことになってしまいます。それはやはりおかしいでしょう。
このような場合、コンプライアンスの要請の高まりや社会の価値観の変化などを理由に、会社が今後の懲戒処分の指針を公表すべきです。例えば、裁判例の中でも、会社がセクハラ行為を許さないという指針を公表し、管理職として研修を受け、十分にセクハラ行為の違法性を認識していた社員がセクハラ行為に及んだことを、懲戒処分の有効性を判断するプラスの要素にしているものがあります。会社としてルールを作り、それを公表し、社員に周知し、根付かせることは、ルール違反があった時に有効な懲戒処分を下す担保になるのです。
今回の事例の場合、実際のところ、当時を知る社員に事情を聴取しても、不正が行われていたと疑うべき事実は確認されませんでした。もし、不正を見聞きして証言する社員が現れたり、帳簿などなんらかの物証から不正が疑われる場合には、退職した元所長のBにまで聴取を要請したり、処分の対象とすべき社員を特定すべきでした。
5 役員による不正の場合
仮に社員ではなく、役員が不正を行っていた場合、役員は雇用契約を結んだ労働者ではないため、就業規則や懲戒処分の規定は適用されません。ですが、取締役は、会社と委任契約を結び、会社の重要な職務を決定したり実行したりする責任を負っています。このような職責のある取締役が不正を行っていたということは、委任契約の趣旨に反することになります。従って職務を全うしなかったことを理由として、役員報酬の返還、減額、損害賠償の請求、役員からの解任などを行うべきでしょう。
6 まとめ
今回の事例では、過去の不正が取り沙汰されましたが、結局は確証がなく、なんらの処分も行われませんでした。もし同様に過去の不正が明るみになった場合、何年前のことかというよりも、その不正が初めて懲戒事案として認識され、調査対象になったのか、既に処分がなされているか、他の同種の事案ではどのように対処したかに注意し、懲戒処分を検討しましょう。
※他の「問題社員対応・解雇」に関する事例は、
▶ 事例集ページ からご覧いただけます。