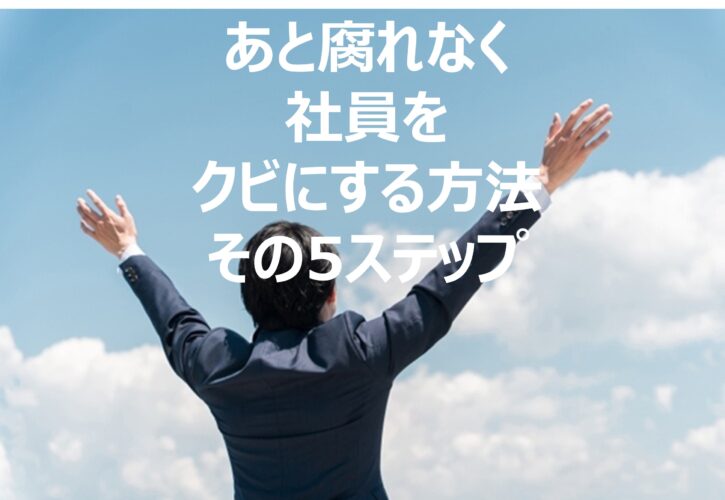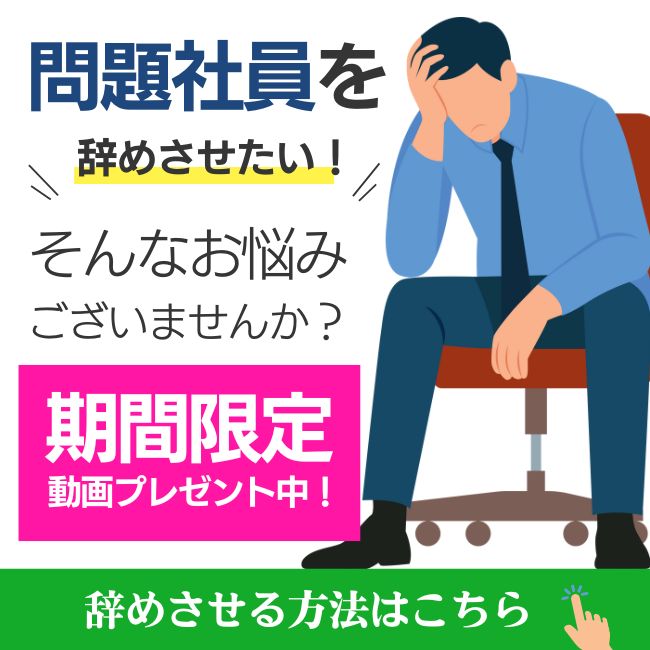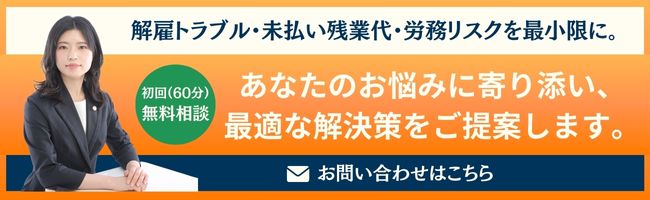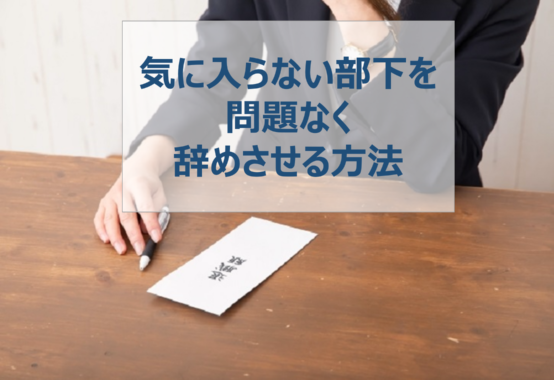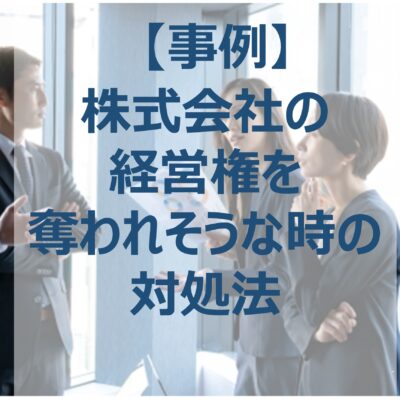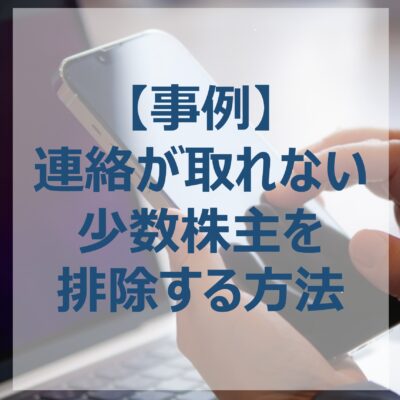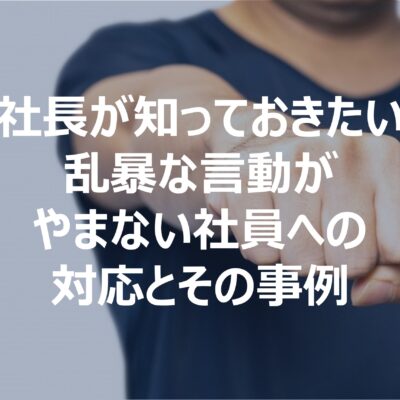正直言って辞めさせたいと思っている従業員がいる。けれど、辞めさせるとなると何かとトラブルになりそう。そんな時、後腐れなく辞めさせるにはどうすればいいか? 5つのステップをご紹介します。
1 辞めさせるまでのポイント
辞めさせるまでのポイントとして、2つ覚えておいてほしいことがあります。
1つは、辞めさせ方のステップとして、初めに自主退職してもらうことを目指し、それがダメな場合に解雇するという二段構えでいくということです。なぜなら、法律上、解雇の要件が非常に厳しいため、解雇を成功させることが難しいからです。そのため、解雇を避けて、まずは従業員が自ら辞めてくれないか、自主退職をしてもらうことを目指すのです。
もう1つは、辞めさせる理由について、きちんと証拠を揃えて用意するということです。初めに自主退職を求めるにしても、従業員本人が納得するような辞めさせられる理由がなければ、うまくいきません。そして、もし自主退職が奏功しなかった場合、次は解雇という手段になるわけですが、解雇をするためには、解雇に値する理由があり、それを証拠で証明できることが厳格に要求されます。したがって、その従業員を辞めさせなければいけない理由について、きちんと証拠を用意しておくことが大切なのです。
2 ステップ1 証拠集め
従業員を辞めさせるためには、きちんと辞めさせるだけの理由があること、そしてそれを証拠で示せることが求められます。どのような理由で辞めさせたいかによって、必要となる証拠も変わってきます。例えば、仕事の出来が悪くミスを繰り返すというのであれば、ミスをした時の記録やそれに対する指導の記録、本人が述べた改善方法などを業務日報やメール等で証拠化します。
証拠は1つあればよい、という訳ではありません。その従業員が同じような問題を何度も繰り返している場合なら、逐一、その証拠を確保しておきましょう。長期間、そして何度も問題行為をしているということが、辞めさせるうえでは会社に有利に働くからです。証拠がない場合には、その問題行為もなかったのと同じです。同じようなことの繰り返しであっても、かならず逐一証拠を確保しましょう。
そして、証拠というのは、辞めさせられる従業員本人が見ても、そして、仮に裁判官が見ても、「これならば辞めるように言われても仕方がない」といえるほどのものを確保するよう努力する必要があります。会社や社長目線で「これくらいの証拠がそろっていればいいだろう」と満足する程度では不十分です。敵対する立場や事情を全く知らない第三者の立場で見たとしても、納得できるほど説得力のあるものを揃えましょう。
3 ステップ2 自覚の促し
辞めさせる理由となる証拠が集まってきたら、それを従業員本人に示し、本人に問題点を自覚させる機会を作りましょう。自分が辞めさせる理由を自覚しないままでは、自主退職も望めませんし、解雇をしても紛争になります。
横領など、即解雇すべきような場合は話は別ですが、本人に問題点を自覚させる機会は、繰り返し作りましょう。その際、会社は辞めさせようという意図を示すのではなく、「このままの状態で働き続けることはできない」「改善してもらわないといけない」という姿勢で臨みましょう。最初から辞めさせる意図があることが見透かされると、相手は警戒し、紛争化していきます。また、即解雇すべき事案でもない限り、会社が改善に向けて十分な指導を行っていたかどうかも、解雇の有効性を判断する要素になります。
そのため、問題行動の証拠を集めるだけ集めて、最後にすべてを示し、「辞めなさい」というのではなく、ある程度集まるごとに本人に示して面談をし、改善指導を行い、問題行動があるごとに指導を繰り返すようにしましょう。
4 ステップ3 自主退職の勧め
本人に問題行動の自覚をさせ、「ここまで言われているのに、自分は改善できていない」「辞めることになっても仕方ない」と思わせるに至ったら、「辞めてはどうか?」と打診する退職勧奨を行いましょう。これは、あくまで自分から「じゃあ辞めます」というきっかけを作るものですから、従業員本人が自主退職を拒否する場合には、退職を強要してはいけません。従業員から拒否された後に退職勧奨を迫り続けた場合、退職強要して無理に辞めさせたとみなされる可能性があるので、注意が必要です。
5 ステップ4 懲戒
ステップ3で自主退職に応じない場合には、解雇を視野に入れることになります。そのためには、いきなり解雇に持ち込むのではなく、問題行動があった場合に懲戒を行うことも必要です。懲戒歴があるということは、解雇の場面で会社にとって有利に働きます。
また、自主退職に応じるよう働きかけている時点であっても、従業員に懲戒に値するような問題行動があれば、きちんと懲戒をしましょう。懲戒をせずに見逃していると、同じような問題行動を起こした時に、「前回は見逃したのに、なんで今回は懲戒なんだ」と懲戒を実行できないジレンマに陥ります。
結論的に、懲戒に値するような問題行動があった場合には、どのような状況でも、きちんと懲戒を実行しましょう。
6 ステップ5 解雇
解雇すべきような問題行動があり、自主退職にも応じない場合には、最後の手段として解雇に踏み切ることになります。冒頭でも触れましたが、解雇を成功させる法律の要件は、とても厳しいものです。
具体的には(1)解雇の客観的合理的な理由があること(=雇用を継続できない、解雇に値するだけの理由があること)、(2)解雇に社会的相当性があること(=解雇以外に他に手段がないこと)が必要になります。
なかでも(2)解雇に社会的相当性があること(=解雇以外に他に手段がないこと)という要件はとても厳しく、検討をすると、何らかの理由で「解雇以外にもっとこういう手段を講ずべきだった」といえてしまうことが大半です。解雇を実行するためには、ステップ1~4を辛抱強く繰り返さなければいけません。それには、1年、2年の歳月がかかることも決して珍しくありません。
7 まとめ
後腐れなく辞めてもらうためには、辞めさせられる従業員も納得できるような、それだけの理由や説明の過程が必要になります。法律上の要件が厳しいので、安易な解雇は禁物です。遠回りに感じるかもしれませんが、結局はそれが、裁判沙汰の紛争を防ぎ、穏便かつ最速で事態を解決する手段になるのです。